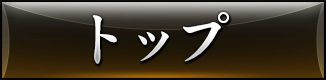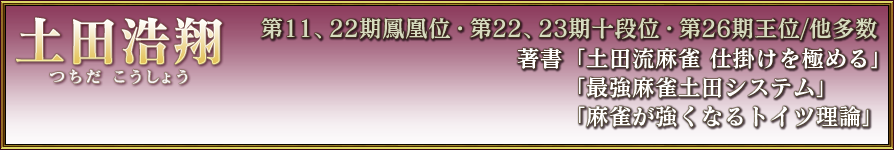
第六十二打「<形式テンパイ>の是非」 2024/05/20
中盤から終盤にかけて、打ち手は和了したい気持ちは持続しつつ『この手はテンパイ止まりなのかな?』と思いはじめます。
たとえば次の手牌
東2局東家の11巡目が終わった時点でのもので、まだ子方からは仕掛けもリーチも入っていない状況です。
テンパイに必要な牌は
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ストレートにこれらの牌たちが入ってきてくれればいいのですが、うまくいくケースより、![]() や
や![]() が重なったりして、狙いの方向性が見えにくくなったりします。
が重なったりして、狙いの方向性が見えにくくなったりします。
ツモ![]() ときたケースでは
ときたケースでは
![]() と
と![]()
![]() の吟味が必要になります。
の吟味が必要になります。
どちらが山にありそうか・・・?
ツモ![]() のケースでは
のケースでは
![]() と
と![]()
![]() の吟味が必要になり、場況やその巡目までの相手の手出し牌を思い出しながら山読みをします。
の吟味が必要になり、場況やその巡目までの相手の手出し牌を思い出しながら山読みをします。
![]()
![]() が良さそうであれば、
が良さそうであれば、![]() や
や![]() を雀頭に切り替えるプランを遂行するわけですが、
を雀頭に切り替えるプランを遂行するわけですが、![]() を雀頭に見立てるケースでも、打
を雀頭に見立てるケースでも、打![]() として
として![]() 引きには備えますし、
引きには備えますし、![]() を雀頭に見立てるケースでも同様に
を雀頭に見立てるケースでも同様に![]() を切って
を切って![]() 引きに備えます。
引きに備えます。
なぜそうするのかと問われれば、残り5〜6回のツモで有効牌が3つあれば和了できて、2つあればテンパイできるからです。
ただ、みなさんの経験で残りツモ5〜6回でリャンシャンテンの手牌が和了できる確率はどれくらいあるのか?記憶を紐解けばそう多くない(ほとんど無理レベル)ことはお分かりいただけるはずです。
残りツモが3回あれば、もしかしたら和了できるかもしれないから最後まで諦めるべきではないと考えることは悪いことではありませんが、効率だとか確率だとかを度外視して打つことが打ち手に求められると言えるでしょう。
残りツモ4〜5回くらいになってもまだ手牌が進まずにいたとき
上家から3枚目の![]() が出てきたらチーする人もいるはずです。
が出てきたらチーする人もいるはずです。
この3枚目の![]() をスルーしてしまうと、和了はもちろんのこと、テンパイすら出来ずに終わりそうだから、チーしてイーシャンテンにしておく、もっともな思考に見えます。
をスルーしてしまうと、和了はもちろんのこと、テンパイすら出来ずに終わりそうだから、チーしてイーシャンテンにしておく、もっともな思考に見えます。
ではなぜチーするのか?
局収支を優位に運びたいからでしょう。
流局したときにノーテンで終わると、最悪のケースとしては1人で支払って他家との点差が4千点つきます。
2人ノーテンでも、テンパイしている人との差は3千点つきます。
そんなことが1ゲームのうちに2度も3度も起きてしまったら相当なハンデを背負うことになるから、終盤に入るとテンパイだけを目指す仕掛けが発生しやすくなります。
テンパイだけを目的とするため、手役の無い仕掛けとなる<形式テンパイ>どりに精を出すことになります。
カン![]() をチーして打
をチーして打![]()
カン![]() をチーして打
をチーして打![]()
カン![]() をチーして打
をチーして打![]()
これらのイーシャンテンにしておいて、更なるチーに備えていく<形式テンパイ>はあらゆる局面で重宝されている打ち手にとって当然の戦法になっています。
特に親番における<形式テンパイ>は重要な役割を果たしているようで、和了の見込みなしと早い段階で決断できると、ハーフタイムの9巡目あたりから仕掛けを入れていく戦術眼に優れた打ち手もいます。
七対子の4シャンテン、普通の手では3シャンテンの手牌ですが、局面は南2局の親でマイナス9千点ほどしているピンチ到来の10巡目に上家から![]() が出てきました。
が出てきました。
「チー」、打![]()
![]() も
も![]() も1枚切れでしたから、この動きの狙いとしては、本線が<形式テンパイ>。うまくいけば、678の三色や役牌
も1枚切れでしたから、この動きの狙いとしては、本線が<形式テンパイ>。うまくいけば、678の三色や役牌![]() の重なりなどの変化でうっすらと和了も見えます。
の重なりなどの変化でうっすらと和了も見えます。
この仕掛けの最大の利点は、ドラ![]() を使いきれるチーが出来たことで、子方から見れば
を使いきれるチーが出来たことで、子方から見れば![]()
![]()
![]() が晒されることによって
が晒されることによって
〇 123の三色
〇 マンズの一気通貫
〇 チャンタ
〇 マンズの混一色
〇 役牌の暗刻もしくは後付け
などなど、手役アリの想定をし始めるはずで、親の威光が幅を利かせられるところにあります。
手牌は10巡目が終わって2シャンテンですから、3シャンテンの状況とはガラリと変わった印象もあり、連荘必須の親としては最善の仕掛けを施したと言えるはずです。
ここまでは<形式テンパイ>を仕掛ける側の意図に沿った話ですが、ここからが本題。
その本題とは、<形式テンパイ>は多用すべきではない、という私の持論です。
その理由を挙げておきます。
(一) 手牌が短くなり放銃の危険が高まる
(二) ノーテン罰符に気をとられてはいけない
(三) 仕掛けは敗因を招きやすい
(四) 親だからという理由は使わないほうがいい
(五) 運(ツキ)は上がるより下がりやすい
(一)については<形式テンパイ>どりに関わらず、仕掛けを入れたときのリスクで、最終盤(16巡目以降)手が詰まりやすくなるケースがほとんどです。そんな折、親番維持のために放銃してしまうと致命傷になります。
(二)は局収支の考え方に頭の中が支配され過ぎて本質を見失う危険性を孕んでいます。
和了に向けていろいろな戦法を駆使することが本質に沿うものであって、手役の無いテンパイを目指す打ち方に溺れてしまうと、強さを身につけられない恐れがあります。
(三)は<形式テンパイ>どりに限った話ではありませんが、私の実戦及び解説経験から、多くの敗因はメンゼンで打っているときではなく、仕掛けているときに生じています。
通常の仕掛けでもそうなのですから、<形式テンパイ>どりのケースではそれ以上の敗因が生じやすいので警戒すべきです。
(四)は<形式テンパイ>どりに限らず、いついかなる場合でも、麻雀の打ち方を考えるとき、親子の区別をつけて思考するのはナンセンスだと思っています。
親は連荘できる。
親は子の1.5倍の和了点が貰える。
親は必要以上に警戒され過大評価もされる。
などなどの理由で、親番を迎えると子方にいるときとは打って変わった攻め筋を見せる打ち手も多いようですが、私は賛成しかねます。
なぜかと言えば、親だから和了しやすいわけではなく、親だから放銃しにくいわけでもないからです。
損得勘定から思考すると、親番は有利に運べるという寸法ですが、その思考が身についてしまうと、打ち筋が甘くなり、贔屓目に手牌を眺める習慣になり強くなれません。
(五)については、局ごとのやりとりは運(ツキ)に支配されているので、良い運を持続させた人が勝ちやすいゲームだと思っています。
ところが<形式テンパイ>狙いでの仕掛けを入れると、その局あなたが持っている運はうまくいって平行線で、7〜8割くらい運は下がっていきます。
目に見えない運(ツキ)の話なんて信じようがない人も多いでしょうが、長年、見えないものを見ようとする訓練を重ねてきた身としてアドバイスを送るとすれば、<形式テンパイ>どりで運を下げないことを進言しておきます。
<形式テンパイ>をうまくとれたときの快感は私もよく理解しています。
それでも敢えてみなさんにお伝えしておきます。
<形式テンパイ>はとりにいかないほうが身のためですよ!と。