





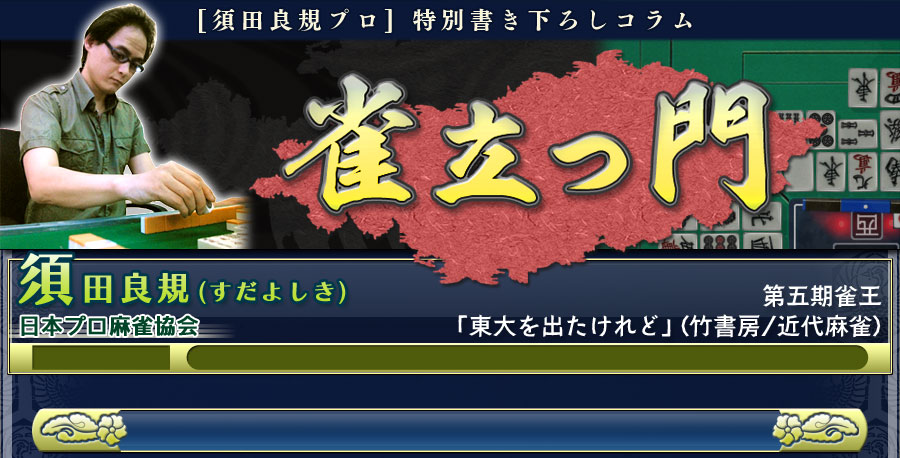
いつものように卓が割れた明け方、私は店のパソコンでMaru-Janを打っていた。古い常連の親爺が、帰ろうともせずそれを見ていた。
「凄え時代になったもんだな」
親爺は興味深そうに画面を見ている。
この親爺との付き合いは長く、その玄人はだしの打ち回しには毎夜苦戦させられていた。まあどこの雀荘でも必ずいる、雀荘の口うるさい主のようなものだ。
主もインターネットの麻雀は初めて見るようで、親爺は子供のように麻雀の新しい世界を注視していた。
オーラス、西家の私は2着の南家と2500点差のトップ目であった。
![]()
「逃げ切れるかな」
親爺が悪戯っぽく笑う。
南家の捨て牌はこうだ。
![]()
![]()
![]()
ドラの![]() を切り飛ばしているため、萬子の混一ではない。明らかにチャンタの仕掛け。500・1000あれば同点上家取りでトップを捲られるので、私もクイタンで応戦した。
を切り飛ばしているため、萬子の混一ではない。明らかにチャンタの仕掛け。500・1000あれば同点上家取りでトップを捲られるので、私もクイタンで応戦した。
中盤に私もこの形。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ここまで役牌は粗方場に打たれており、後は三色を警戒すればよくなった。チャンタのみなら和了られても問題はない。
そして双方和了れぬまま、14巡目に25600点差でダンラスの北家からリーチがかかる。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
親爺の言う通りだ。北家が和了るのが最も望ましいのだが、私が打てば南家より下回ってしまう。私は現物の
次巡、南家が
東家は少考し、手出しで現物を抜いた。ここはノーテンであろう。
流局直前、南家がツモを宣言する。ツモった牌は、地獄の
「ん──?」
この瞬間私達の目には
南家は、チャンタのみの300・500であった。
「これじゃ足りねえぞ」
リーチ棒込みでも、確かに2400点差しか埋まらない。私は100点差、ぎりぎりで逃げ切ったのであった。
安堵する私を尻目に、親爺がやや考えた様子で言う。
「この南家、和了らない方が良かったんじゃないか──」
ああ、そうか。それぞれ残りツモは1回ずつで、私は明らかに降りている。ならば南家はこのツモった![]() を落とせば、次に危険牌を引いても聴牌宣言が出来て、ノーテン罰符で私を捲ることが出来たのだ。
を落とせば、次に危険牌を引いても聴牌宣言が出来て、ノーテン罰符で私を捲ることが出来たのだ。
万一ここで北家がツモ和了っても、倍満だって届かない。東家が聴牌を入れたとしても、私をかわしてトップ目に立って1本場に入れるのだから、このまま2着確定で終わらせるよりはいいだろう。
「こういうの、お前が教えてあげればいいのになあ──」
親爺は古い人間特有の、暖かい表情でしみじみと言った。
昨今はインターネットで麻雀をする人が増えてきて、誰でも自宅で気軽に麻雀を覚えられるようになった。私はずっと雀荘で牌にまみれて生きてきたので、こういう健全な時代の到来を嬉しく思う反面、少し寂しく思うこともある。
雀荘にいると、メンバーや客に海千山千の打ち手が揃っているもので、そうした連中に直接触れていると、麻雀の戦術について学ぶ機会が容易に得られる。インターネットの麻雀も麻雀の勉強にはなるが、直接他の打ち手との意見交換が出来ればもっと上達は早まるだろう。
「そうですね──。Maru-Janには掲示板もあるから、機会があれば。もっとも、嫌味にもならず、打牌批判にもならずに言うのも難しいかもしれないけど──」
「何言ってんだ。他に能なんかないんだから。これぐらいしか、人のために出来ることなんかないだろ」
親爺が軽口を叩いて、笑う。
そういえば私も、これまで親爺からここで沢山のことを学んで来たのである。
打ち手から打ち手へ、麻雀の知識と技術は善意と親愛をもって伝えられて来た。それは古き良き雀荘にある、当たり前の風景であった。
インターネットの麻雀でも、そういう暖かい雀荘らしい交流が再現出来たらな、と思う。私が教わって来たことを、今度は私が教える番だ。
口うるさい、雀荘の親爺も悪くはないさ──。
またな、と出て行く背中を見送って、そんなことを思った。
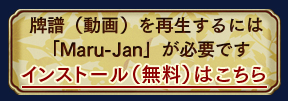
「開く」を押してください。
Firefox、Google Chromeでは、「牌譜ファイルはこちら」を"右"クリックし
保存を行い、その後ファイルを開いてください。








