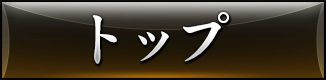





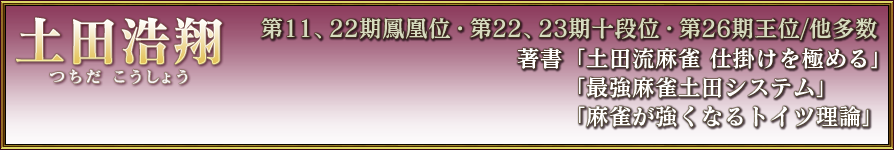
第十三打 「対々和の延長線上に四暗刻は存在しない」2013/11/27
「なにワケわからんこと言ってるんだ。トイトイやってるうちに、あれよあれよと暗刻が増えるから、四暗刻が生まれるんだろ!」とお叱りを受けることは百も承知しておりますが、それでも私は全国津々浦々の麻雀ファンの皆さんに、声を大にして言いたいのです。
『対々和作りと四暗刻作りは全く性質の違う作業になる』 と。
A
B
C
D
A~Dまでの手牌、いずれも南1局の親6巡目終了時のものです。手牌にあるトイツ牌と孤立牌は生牌となっています。
さて、A~Dのうち、四暗刻作りに入ったほうが良い手牌と、対々和作りのほうが良い手牌はどれでしょう?
どれも似たような牌姿になっていますから、ツモってきた牌や場に出てきた牌によって答えが変わると思った方も多いかもしれません。
打点的妙味によって判断される方もいるはずで、役牌![]() がトイツになっているAとD、そしてドラがトイツのCこの3つを対々和狙いにし、Bはのんびりと四暗刻作りに専念するという回答になっている可能性が高いでしょう。
がトイツになっているAとD、そしてドラがトイツのCこの3つを対々和狙いにし、Bはのんびりと四暗刻作りに専念するという回答になっている可能性が高いでしょう。
いろいろな見立てがあってよいのですが、ポンと仕掛けていってよいものか、判断に迷う手牌が並んでいるので、私の見立てをA~Dまでひとつずつお話ししていきたいと思います。
Aは、役牌の![]() がトイツで入っています。そして、
がトイツで入っています。そして、![]() 、
、![]() というポンしやすい牌もトイツで入っています。
というポンしやすい牌もトイツで入っています。
対々和を狙っていく条件は、ポンしやすいトイツをたくさん持っていることと、役牌がトイツで入っていることです。
タンヤオの対々和に関しては、役牌がありませんから、ポンしやすい2や8をどれくらいトイツで持っているかにかかっています。
話を戻しますと、Aの手牌は、対々和を狙っていきやすい素材が揃っていますから、積極的にポンポンと仕掛けていったほうがいいと思います。
Bは、対々和狙いの武器である役牌がありません。でも、ポンしやすい素材の![]()
![]()
![]() をトイツで持っていますから、親の威光でポンポンと仕掛けていく手もありますが、この手牌は四暗刻のビッグチャンスとなっていることに注目して欲しいのです。
をトイツで持っていますから、親の威光でポンポンと仕掛けていく手もありますが、この手牌は四暗刻のビッグチャンスとなっていることに注目して欲しいのです。
Aの手牌にある暗刻牌は![]() ですが、Bは尖張牌の
ですが、Bは尖張牌の![]() が暗刻になっています。この[尖張牌の暗刻]は、四暗刻作りのGOサインと考えていい指標で、他家のシュンツ手が作りにくくなるぶん、四暗刻が成就する時間が稼げるのです。
が暗刻になっています。この[尖張牌の暗刻]は、四暗刻作りのGOサインと考えていい指標で、他家のシュンツ手が作りにくくなるぶん、四暗刻が成就する時間が稼げるのです。
この手牌のように、すでに尖張牌である![]() が暗刻になっているツモり四暗刻リャンシャンテン形においては、手中にあるトイツ牌が場に枯れても、ポンせずにメンゼンでいく胆力が必要となります。
が暗刻になっているツモり四暗刻リャンシャンテン形においては、手中にあるトイツ牌が場に枯れても、ポンせずにメンゼンでいく胆力が必要となります。
つまり、Bの手牌においては、暗刻牌![]() 以外のトイツ牌、
以外のトイツ牌、![]()
![]()
![]()
![]() の4組のうち3組を自力で暗刻にするんだという意志力が問われているのです。
の4組のうち3組を自力で暗刻にするんだという意志力が問われているのです。
Bの手牌が次のようなイーシャンテンになったとき
![]()
![]()
![]() のどれかひとつが場に枯れても、渋々ポンして対々和に向かわず、残り2組と孤立牌の
のどれかひとつが場に枯れても、渋々ポンして対々和に向かわず、残り2組と孤立牌の![]() を頼りに(もし
を頼りに(もし![]() が暗刻になる可能性が消えたときは、新たな可能性を求め、暗刻になりそうな孤立牌にチェンジする)、対々和ではなく、あくまでも四暗刻を仕上げるつもりで打っていく胆力が求められるのです。
が暗刻になる可能性が消えたときは、新たな可能性を求め、暗刻になりそうな孤立牌にチェンジする)、対々和ではなく、あくまでも四暗刻を仕上げるつもりで打っていく胆力が求められるのです。
Cは、尖張牌の![]() がドラになっていて、
がドラになっていて、![]() が暗刻という手牌ですが、実は七対子のイーシャンテンにもなっています。
が暗刻という手牌ですが、実は七対子のイーシャンテンにもなっています。
![]()
![]() というポンしやすい牌がトイツになっているものの、ドラがトイツの手牌は、基本的には七対子優先で打ったほうがいいと思います。
というポンしやすい牌がトイツになっているものの、ドラがトイツの手牌は、基本的には七対子優先で打ったほうがいいと思います。
なぜかと言いますと、ドラがトイツの七対子は、裏ドラが乗ると倍満にまで化ける打撃系の手役なので、対々和狙いにして3枚目のドラにも頼ってしまうような打ち方より、七対子に決め打ちしたほうが得策です。
もちろん、ドラの![]() が暗刻になるような展開になると、いつもの尖張牌暗刻より数倍の四暗刻エネルギーが働きますから、10巡目まではこのままの形(トイツ4組、暗刻1組)で打ったほうがいいでしょう。
が暗刻になるような展開になると、いつもの尖張牌暗刻より数倍の四暗刻エネルギーが働きますから、10巡目まではこのままの形(トイツ4組、暗刻1組)で打ったほうがいいでしょう。
そして10巡目になっても暗刻が増えてこなければ、暗刻の![]() を1枚切って、孤立牌3枚残しの七対子イーシャンテン手牌に構え、四暗刻への未練をたちましょう。
を1枚切って、孤立牌3枚残しの七対子イーシャンテン手牌に構え、四暗刻への未練をたちましょう。
Cの手牌が6巡目の段階で
こうなっていたのであれば、四暗刻への道は選ばず、即座に暗刻の![]() を1枚切って、七対子一本で戦うべきです。
を1枚切って、七対子一本で戦うべきです。
それほどまでに、尖張牌(3と7)の存在が四暗刻作りに大きな影響を与えているということなのです。
ではDはどうでしょうか。
A同様に役牌の![]() がトイツで入っている手牌ゆえ、ポンポンと対々和に向かったほうが良さそうに見えますが、Aの手牌との違いにも気づくべきです。
がトイツで入っている手牌ゆえ、ポンポンと対々和に向かったほうが良さそうに見えますが、Aの手牌との違いにも気づくべきです。
Aは![]() が暗刻で、
が暗刻で、![]()
![]()
![]()
![]() がトイツ牌です。
がトイツ牌です。
Dは![]() が暗刻で、
が暗刻で、![]()
![]()
![]()
![]() がトイツ牌です。
がトイツ牌です。
ポンしやすい牌がAは3種あるのに対し、Dは2種しかありません。この1種の違いは、対々和狙いに踏み込む場合、その成功率の違いとなって結果に表れてきます。
ですからDは条件付きでの対々和狙いになります。
つまり、ポンと初動をかける牌をポンしにくい![]()
![]() に限定してしまうのです。
に限定してしまうのです。
![]() か
か![]() からポンと仕掛けることが出来れば、残されたトイツ牌はAの手牌と同じく、ポンしやすい牌3種が残り、成功率は格段にアップするでしょう。
からポンと仕掛けることが出来れば、残されたトイツ牌はAの手牌と同じく、ポンしやすい牌3種が残り、成功率は格段にアップするでしょう。
また、ポンしたい牌が出る前に、![]() が暗刻になってくれれば、今度は対々和ではなく、Bの手牌より更に1歩進んだ四暗刻手牌に大化けしてくれるのです。
が暗刻になってくれれば、今度は対々和ではなく、Bの手牌より更に1歩進んだ四暗刻手牌に大化けしてくれるのです。
先日もこんなことがありました。
南1局の親番で、1万点くらい沈んだ3番手にいた私は、7巡目に出た![]() をスルーして四暗刻に照準を定めていました。
をスルーして四暗刻に照準を定めていました。
すると、9巡目に![]() を引きテンパイを果たし、ツモり四暗刻テンパイの常道となるリーチ宣言し〈場〉をロックしました。
を引きテンパイを果たし、ツモり四暗刻テンパイの常道となるリーチ宣言し〈場〉をロックしました。
〈場〉をロックするとは、四暗刻に限ったことではありませんが、親・子にかかわらず、高打点手牌をテンパイしたらリーチをかけ、〈場〉に緊張感を走らせ、他家の打牌に制約をかける考え方です。
私の経験上、〈場〉にロックをかけたほうが和了率はアップします。
普通の思考でいけば、リーチをかけてしまったら、ポロッと打ち出される牌も出てこなくなり、和了率は下がってしまうと考えがちですが、こと高打点手牌に関してはその範疇にはありません。
11巡目、下家がちょっとコワゴワ2枚目の![]() を打ってきましたがスルー!!
を打ってきましたがスルー!!
ロンしてしまえば、ただの対々和プラス三暗刻で終わり、せっかくの尖張牌![]() 暗刻をフイにすることになります。
暗刻をフイにすることになります。
もちろん、スルーしてアガれる保証なんてどこにもありません。
もったいないと思われる方がたくさんいて当然です。
でも、『対々和の延長線上に四暗刻は存在しない』ことを知っていれば、リーチ後の見逃しもなんのその、![]() をスッとツモってくることも多々あるのです。
をスッとツモってくることも多々あるのです。









