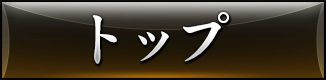





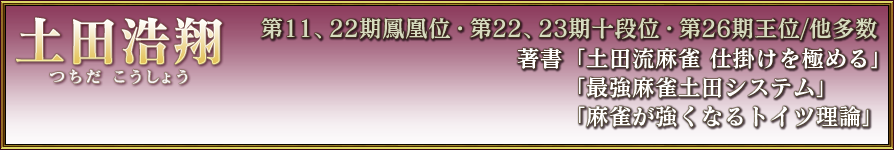
第三十八打「河は生きもの」 2018/02/09
<河>を見ずに打てるだろうか?
そんなふうに思いながら打ち始めてみても、3~4巡たつと知らぬ間に下家やトイメンの<河>が目に飛び込んできます。
私の習性なのか、上家の<河>は2~3巡遅れて視界に入ってきます。
<河>のことを一般的には<捨て牌>と呼んでいますが、私の好みとしては<河>と呼びたくなってしまいます。
それは136枚の牌たちと向き合うときに、14枚の中から1枚いらないと思う牌を選ぶわけですが、その行為を「捨てる」とは言わずに「切る」と言っていることに準じています。
私は、手の中にある牌たちも、<河>に並べていく牌たちも、同じ手牌にあって仲間なんだという見方をしています。
ですから、「捨てる」という表現には何か違和感を覚えてしまうのです。
話を戻しましょう。
意識しようとしまいと、<河>は麻雀を打っていくうえで、自分の方向性を左右する重要な役割を担っていることは間違いありません。
今回はその<河>の見立てについて、具体例を挙げながら触れてみたいと思います。
<河>に付けてある×印はツモ切り牌であることを表しています。
このツモ切りと手出しの区別は、<河>を考えるうえでとても重要なポイントです。
もちろん、ツモ切りと手出しを全て記憶することは至難のワザですから、手出しの牌を見ておくことが大事な一歩となります。
一般的に、よほどのヘソ曲がりでないかぎり、そこそこの配牌をもらえた時の切り順は似通ってくるものです。
孤立字牌⇒孤立1・9牌⇒孤立2・8牌
孤立1・9牌⇒孤立字牌⇒孤立2・8牌
昭和の打ち手の中には(私などその典型ですが)、孤立牌を切りながらも、リャンメン形を決め打つダブリ牌を切ったり、トイツの一部を切り離す浮かせ打ちを織り混ぜたりしますが、それはレアケース。
先に挙げた<河>は
これが現代流では
このように役牌⇒オタ風の切り出しになっているケースも多く見られます。
いずれにしても、![]() と
と![]() という1・9牌のツモ切り直後にタンヤオ牌の
という1・9牌のツモ切り直後にタンヤオ牌の![]() が手出しされたことから、この打ち手の手牌には、孤立している1・9牌が無いという読みを入れることができます。
が手出しされたことから、この打ち手の手牌には、孤立している1・9牌が無いという読みを入れることができます。
ただし、手牌進行速度としてはB~Cランクで、著しく速い手牌になっているとは思えません。
この<河>が
こうなっていたら、手牌進行速度はAランクで打点も伴うリーチが2~3巡以内にかかって不思議ではない、ということになります。
なぜなら、タンヤオ牌の![]() をツモ切りできていること、ドラそばの
をツモ切りできていること、ドラそばの![]() が手出しされていること、数牌の3色目(ピンズ)が手出しされ、それが3~7までの要牌である
が手出しされていること、数牌の3色目(ピンズ)が手出しされ、それが3~7までの要牌である![]() であること、以上の3つの理由から、この<河>の恐ろしさが読み取れるのです。
であること、以上の3つの理由から、この<河>の恐ろしさが読み取れるのです。
<河>の速さという点について一般化しておくと、以下のような現象が見られたら、注意を払ったほうがいいでしょう。
(1) 1・9・字牌から始まる<河>が、3~4巡目あたりからタンヤオ牌が手出しされる
(2) 手出しされるタンヤオ牌に、3~7までの要牌が含まれる
(3) ドラそばの牌が早めに手出しされる
(4) マンズ・ピンズ・ソウズ3種のタンヤオ牌が7~8巡目あたりまでに手出しされる
(5) カンチャン・リャンメンターツを7~8巡目あたりまでに外してくる
次にこの<河>はいかがでしょう。
タンヤオ牌からの切り出しで、5・6巡目に字牌が手出しされています。
この<河>が東家や南家のものであったとしたら、オタ風の![]() と
と![]() の手出しをどのように読むべきでしょうか?
の手出しをどのように読むべきでしょうか?
とくに、![]() が生牌、
が生牌、![]() が1枚切れだったとしたら、果してどんな意味があるのか?
が1枚切れだったとしたら、果してどんな意味があるのか?
考えてみると面白くなってきます。
そもそも序盤にタンヤオ牌が並び、一色手でもなさそうにみえる<河>、更にはそれらタンヤオ牌の後から字牌が手出しされてくる<河>とは?どんな指向なのでしょう。
まず浮かぶのは七対子、次にチャンタ、そして暗刻手あたりでしょうか。
つまり、ある手役を指向したときに、字牌を使用したら便利かなと思えるケースです。
そして、その便利に思える字牌が、早い段階で<河>に姿を見せるということは、それだけ手牌進行しているという証しであり、警戒警報が発令されたも同然なのです。
![]() が生牌、
が生牌、![]() が1枚切れであったならば、チャンタや暗刻手より七対子指向のほうが濃い<河>という読みになります。
が1枚切れであったならば、チャンタや暗刻手より七対子指向のほうが濃い<河>という読みになります。
もし自分が七対子を指向して、イーシャンテンあたりまで手牌進行したとき、生牌と1枚切れの字牌、どちらを手元に残すか?ということを考えてみてください。
逆に七対子指向ではなく、チャンタや暗刻手を狙っている場合は、トイツではなくコーツとしての字牌に魅力を感じるので、1枚切れよりも生牌を温存するはずです。
すると<河>は敏感に反応して
ではなく
となっているのです。
では次の<河>はどんなふうに読みますか?
普通に読めばピンズの一色手指向の<河>ということになります。
七対子の可能性も否定できませんが、7巡目以降の手出し牌にマンズやソーズがなければ、90%ピンズの一色手でしょう。
さて、一色手の速度判断をするときには、字牌がカギとなることが多いので、その字牌が何枚切れかに注目してください。
自身が一色手を作っているときを思い浮かべれば理解できることがあります。
それは、1枚切れや生牌の字牌を<河>に切るタイミングです。
かなり手牌が煮詰まってこない限り、1枚切れや生牌の字牌には手をかけないのではないでしょうか。
この手出しされた![]() が生牌であったなら要注意です。
が生牌であったなら要注意です。
テンパイはもうすぐそこまで来ているので、次にピンズが手出しされたらほぼテンパイ、字牌が手出しされたなら、イーシャンテンもしくはテンパイということになっています。
ただしこの![]() が2枚切れや3枚切れの牌であったならば、まだリャンシャンテンあたりという読み方でいいのですが、次に手出しされる字牌には注意を払う必要があります。
が2枚切れや3枚切れの牌であったならば、まだリャンシャンテンあたりという読み方でいいのですが、次に手出しされる字牌には注意を払う必要があります。
<河>を読むということは、イコール相手のことを考えるということになります。相手は自分と違う人間ですから、思考や感性の違いが<河>に出て、読んでも読み切れないのは当然です。
でも、速さのある手牌は似てきます。
好き嫌いは抜きに、早くアガれそうだと思うと、人間であるかぎり、手牌に素直になるものなのです。
そうなると<河>も素直なものとなり、読みが通じるケースも増えてくるものです。
いかがですか。
<河>の見立てを楽しまれてみては。









