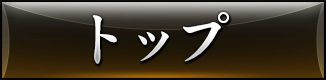





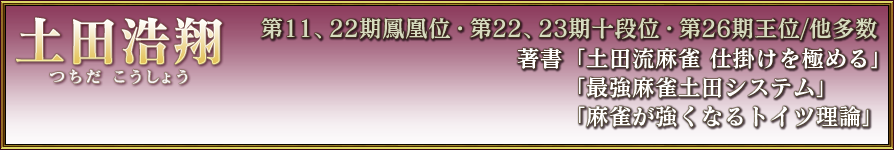
第三十九打「システムを利用する」 2018/05/09
東3局東家8巡目の選択です。
マンズのリャンカン形が先に埋まってくれればいいのになと思っていたところに、ピンズが嬉しい形になるツモ![]() 。
。
アガりがぐっと近づいた感触になり、手拍子で![]() に手がかかりそうになるところでしたが、ソーズの下目も山にありそうで、
に手がかかりそうになるところでしたが、ソーズの下目も山にありそうで、![]() 引きのテンパイも視野に入れて
引きのテンパイも視野に入れて![]() を切りました。
を切りました。
このリャンカン形をテンパイする前に決める選択は、場況に従うケースと<システム>に従うケースに分けています。
<システム>という言葉に疑念を抱く方もいらっしゃるでしょうが、ゲーム中、迷いを消して心の揺れをできるかぎり減らすための処方箋です。
この処方箋はけっこうな種類キープしていて、対局中にムクムク頭をもたげ始める私の揺れを抑えてくれています。
リャンカン形の<システム>は、2~5~8の筋を頼りに処方されていて
〔135〕⇒5切り
〔246〕⇒2切り
〔468〕⇒8切り
〔579〕⇒5切り
というように、待ち方が2~5~8のどれかになります。
先々の変化をみて、46という形にするのではなく、そのまま即リーチが打てるように決め打っておくのです。
では〔357〕の形はどうするのか?
これは迷うことなく、5を先切りし、3や7という尖張牌のどちらかが活きるよう、両方孤立させておきます。
3に2や1がくっつけば7切り、7に8か9がくっつけば3切りとし、一手先に固定させる<システム>なのです。
もちろん〔357〕から5を切った直後に裏目の4や6を引いてくることもありますが、Bリャンメン(※)のフリテンなので、そのままフリテンキープをします。
(※Bリャンメンとは土田プロが説くリャンメンの格付け。参考「麻雀のすべて」)
裏目を引いても揺れないこと。これはもう打ち手に課せられた責務かもしれませんね。
七対子の<システム>についても触れておかなければなりませんね。
東3局南家7巡目の手牌です。
関連牌は場に![]() が1枚だけ出ています。
が1枚だけ出ています。
さて何を切りますか?
七対子とイーペーコーは仲が良くて、<対子場>で現れやすい手役の代表です。
できれば手役の加算をして欲しいくらいで、リーチ・七対子・イーペーコー・ドラ2で出アガりハネ満!になってくれればいいなと、いつも無いものねだりをしています。
私の<システム>からは![]() 切り。
切り。
イーペーコー部分だから、![]() は引きやすいはずなのでは?と思われている方がいらっしゃったとしたら私の説明不足だったかもしれません。
は引きやすいはずなのでは?と思われている方がいらっしゃったとしたら私の説明不足だったかもしれません。
七対子を狙うとき、もし手中にイーペーコーになりそうな5枚形があったならば、カンチャンイーペーコー形だけは大切に扱ってください。
場況が味方していない限り、リャンメンイーペーコー形〔23344のような〕やペンチャンイーペーコー形〔11223のような〕が完成して、七対子の助っ人になるとは考えないほうが賢明です。
また、七対子<システム>にある<スジトイツ>については、近いスジ同士が重なり合うことはあっても、場況が味方していない限り、1と7、2と8、3と9のように、遠いスジは重なりにくいと覚えてください。
ですからこの七対子イーシャンテン形から切る牌は、ペンチャンイーペーコー形であり、すでにトイツの![]() から遠いスジに当たる
から遠いスジに当たる![]() が第1候補になるのです。
が第1候補になるのです。
第2候補は、![]() のスジ
のスジ![]() 、
、![]() のスジ
のスジ![]() をキープすると考えれば、自動的に
をキープすると考えれば、自動的に![]() が手牌から放出される<システム>となっているのです。
が手牌から放出される<システム>となっているのです。
では次の手牌はどうでしょうか?
東4局5巡目、親の手牌です。
![]()
![]()
![]() ともに1枚ずつ出ています。
ともに1枚ずつ出ています。
ドラの![]() は生牌です。
は生牌です。
まず、ドラの取捨についてですが、私の<システム>はこうなっています。
(持ち点)
▲3千以上 ドラ待ちリーチも辞さず
▲8千以上 テンパイまで重ならなければ、ドラ切りリーチ
▲1万2千以上 6巡目までに重ならなければ放出
▲1万6千以上 2巡目までに重ならなければ放出
この<システム>に従ってドラ![]() を取捨選択します。
を取捨選択します。
細かい話をすれば、▲1万3千、▲1万4千、▲1万5千で、5巡目→4巡目→3巡目と、大まかにドラ放出期を決めています。
では決めている巡目以降にドラを引かされてしまった場合は?
▲9千→11巡目、▲1万→10巡目、▲1万1千→9巡目、▲1万2千→8巡目……と、放出限界巡目を決めておき、その限界巡目を超えてドラを引かされたら、たとえイーシャンテンでも粘らず即撤退します。
それでは次に字牌の![]()
![]()
![]() の選択についてですが、これはもう<字牌切りシステム>に従うしかありません。
の選択についてですが、これはもう<字牌切りシステム>に従うしかありません。
<字牌切りシステム>とは?
〔三元牌〕
![]() →
→![]() →
→![]() の順で切ります。
の順で切ります。
調子が落ちてくる度合いに従って
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
と、切り順を変化させます。
<システム>なので、場に切られている枚数が同じときだけに採用されます。
その意味においては、生牌、1枚切れ、2枚切れの切り順についても<システム化>しています。
ただし、手牌進行上、共通安全牌を抱えておきたい等々、明確な理由があるケースにおいては<システム>は発動しません。
基本的には、1枚切れ→2枚切れ→生牌の順で処理していきますが、調子が落ちてくる度合いに従って
2枚切れ→1枚切れ→生牌
1枚切れ→生牌→2枚切れ
生牌→1枚切れ→2枚切れ
と切り順を変化させます。
〔風牌〕
風牌は、自分から見て3種に分かれます。
〔場風〕・〔自風〕・〔オタ風〕です。
まず、この切り順は基本的に
オタ風→自風→場風としていて、調子が落ちてくる度合いに従って
オタ風→場風→自風
自風→オタ風→場風
自風→場風→オタ風
場風→オタ風→自風
場風→自風→オタ風
と切り順を変化させます。
では、オタ風同士の取り扱いについてはどう<システム化>しているのかと問われれば
東家の場合には、![]() →
→![]() →
→![]()
南家の場合には、![]() →
→![]() →
→![]()
西家の場合には、![]() →
→![]() →
→![]()
北家の場合には、![]() →
→![]() →
→![]()
としていて、調子が落ちてくる度合いに従って、三元牌と同じように変化させます。
東4局の親の手牌なので、1枚切れとなっている風牌はすべてオタ風ですから、<システム>に従って選択すれば、平時であれば![]() →
→![]() →
→![]() (1枚切れであり続けるかぎり)の順で放出していきます。
(1枚切れであり続けるかぎり)の順で放出していきます。
そして東4局といえども、すでに調子が下降している状態では、その度合いに従って
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
![]() →
→![]() →
→![]()
と放出する順を変えて打っていきます。
<システム化>すれば問題が解決されるのか?と問われれば、うまくいくことのほうが若干多くなるとしか云えません。
でも、この<システム化>の大きな利点は、「迷わずに打てる」というところにあります。
すべからく、心の揺れが選択眼を濁らせるわけで、負の連鎖の起点が「迷い」であるならば、その「迷い」を消すための<システム化>は、打ち手にとっての生命線になるのではないか、私はそう考えているのです。









