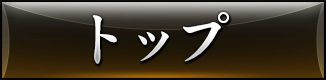





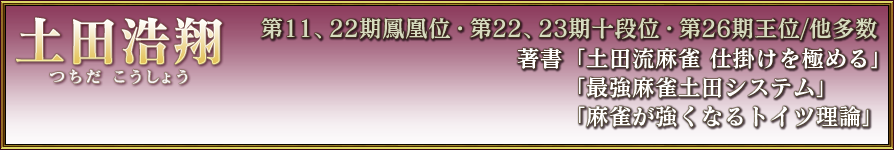
第四十八打「解説の仕事」 2020/07/30
プロとして今の私は何をなりわいとしているのかと問われると、まずは教室の講師として糧を得ていると答えるはずです。
・NHK文化センター
・ホテルニューオータニ
・大阪リーガロイヤルホテル
この3つの教室では主に初心者から初級者の方々に麻雀のイロハをお伝えしています。
・セラピー教室
・東京麻雀アカデミー
・博多麻雀アカデミー
・広島麻雀アカデミー
・大阪麻雀アカデミー
・札幌麻雀アカデミー
この6つの教室では主に中級者から上級者の方々に麻雀の精神論をお伝えしています。
精神論と書いてしまうと少し大上段な構えに見えてしまうかもしれませんね。
実はそんなに難しい話をしているわけではなくて、「また一緒に卓を囲みましょうね」と相手から思ってもらえる打ち手を目指そうという話をしているだけなのです。
トップを取ることよりも、ラスを引かないことよりも、勝つことよりも、アガることよりも大切なことがあるのでは?という想いを来られた方々に伝えている時間です。
教室以外では、全国津々浦々からゲストで呼ばれることも、プロとしての糧を与えていただいた貴重な時間だったのですが、打ち手としての価値が下がるとともに、めっきり少なくなりました。
原稿にしてもそうです。
読者の皆さんに価値ある一品を提供できれば良いのですが、昭和から平成に移り、平成から令和に移りと、時代は確実に流れていて、その時代にマッチした一品を提供できないプロは採用されにくいものです。
でもそんな私にも救いの手は差し伸べられていて、これはもう本当にラッキーな話なのですが、<解説者>としての道が残されていたようなのです。
私が初めて解説をさせていただいた番組は「モンド麻雀プロリーグ」でした。
今から四半世紀前のことです。
土屋アナがうまく私の特徴を引き出してくれたおかげで、自分でも知らなかった一面に気づくことができました。
以来、「THEわれめDEポン」、「極雀」、スリアロチャンネルの「四神降臨」、「麻雀の鉄人」等々、プロとしての糧を得る以上の貴重な体験をさせていただきました。
そして「Mリーグ」
この番組へのオファーは、私の晩年の設計図を大きく変えてくれるものになりました。
名だたる企業を背に打つ一流プロたちの競演、これ以上ない舞台の解説を担う責任の重さはあったものの、自身のプロ人生の集大成と捉えると、無上の喜びと思えたのです。
と同時に、自分の麻雀力の足りなさが露見する可能性もあり、断崖に立たされたような恐怖心に駆られたことも確かです。
実際「Mリーグ」での解説を始めてみると、想定外の局面が起きました。
南場に入って2番手にいた親が9巡目にリーチをかけてきました。
ありふれたピンフ・ドラ1リーチです。
終盤までにツモれず、流局濃厚かと思った17巡目、北家が西家の切った![]() をチー。
をチー。
北家の手牌はと言うと
リーチ直後からガードに徹していた北家のバラ手からのチーに私は一瞬息を呑み、2〜3秒の空白が生じてしまいました。
あとから考えれば、北家のチーには相応な理由があったにも関わらず、一瞬でも沈黙してしまった自分が情けないかぎりです。
実はこのゲーム、トップ争いもさることながら、3番手の北家とラス目の西家も大接戦だったので、親リーチに対して危ないとは言えないまでも、スジ牌を2種類切っていた西家が北家にはテンパイに見えたのでしょう。
実際の西家は手詰まりしていて、仕方なしにスジを頼っていただけなのですが、北家としてはノーテン罰符のやりとりでラス目に転落する恐れもあり、通常なら南家がツモる海底牌(ハイテイハイ)を西家に回して困らせたかったという理由だったのです。
ところが、その北家のチーの直後、親が![]() をツモアガり、裏ドラも乗って4000オールのアガりとなったため、その北家の意図を即座に伝えられず、トップ争いをしていた南家のファンから見れば、「北家がワケ分からんチーしたから」という思いを抱いてしまったのは当然だったかもしれません。
をツモアガり、裏ドラも乗って4000オールのアガりとなったため、その北家の意図を即座に伝えられず、トップ争いをしていた南家のファンから見れば、「北家がワケ分からんチーしたから」という思いを抱いてしまったのは当然だったかもしれません。
麻雀力の高さは言うに及ばず、その能力を一瞬で放つ瞬発力も解説者には求められるわけで、ましてや「Mリーグ」という舞台での失策、今でも穴があったら入りたい気持ちです。
記憶に残るところではもうひとつ。
東場の南家のプレーについて。
まだ各家とも点数の開きはなく、きわめて平坦な局面でした。
5巡目のことでした。
南家は北家の切った生牌の![]() をポンしたのです。
をポンしたのです。
![]() も
も![]() もまだ生牌です。
もまだ生牌です。
「あらら」、私はなんとも表現のしようのない奇声を上げていました。
打![]()
残された手牌はといえば
確かに![]() 後付けのイーシャンテン手牌にはなっていますが、ドラの
後付けのイーシャンテン手牌にはなっていますが、ドラの![]() がそう易々と出てくるものでしょうか?
がそう易々と出てくるものでしょうか?
かと言って、マンズの一色に染めるにはひと手間もふた手間もかかってしまいます。
7巡目、親が![]() を切ると、これもポン、打牌は
を切ると、これもポン、打牌は![]() 、そして次巡
、そして次巡![]() も河に並べたではありませんか。
も河に並べたではありませんか。
私もボンクラです。
このチャンタ志向に気づけないんですから。
これはもう瞬発力というより麻雀力の問題で、いくら4者の手牌に気をとられているとはいえ、「Mリーグ」の解説者としてはあってはならないことでした。
解説者の心得とは
1.わかりやすいこと
2.聞きやすいテンポで
3.常識的な日本語で
4.誰かに肩入れせず客観的に
5.短所は控えめに長所を大に
6.打ち手の心情に寄り添う
7.打ち手の思考を伝える
8.楽しいこと
まだまだあるのかもしれませんが、私が解説をする際に心がけていることはこの8項目です。
それでもうまく話せないことが多くて、番組が終わってからの脱力感と自己嫌悪感はハンパではありません。
プロであるならば、ツイッター・フェイスブック・インスタグラムなどのSNSを駆使してファンの皆さんの生の声を目にすべきなのでしょうが、自己嫌悪感が増幅することを恐れてしまう弱虫なのです。
それでも解説の仕事は大好きです。
教室の仕事は、直接生徒さんやファンの方々とふれ合うことができて、「自分はなんて幸せなんだろう」という実感がもてる意味において、至福の職と言えるのですが、生来、人と接することがあまり得意ではない性格なので、それなりのプレッシャーがあります。
翻って解説の仕事は、なんか自分の性格に合っていて、様々な失敗談や能力不足は置いておけば、プロとして一番やっていたい仕事なのかもしれません。
ファンの方々から、「いつも見てるよ(正しくは聴いてるよ)」とか「面白いよね〜アンタの解説」とか「家族で笑わせてもらってます」と話しかけられる時に思います。
「麻雀プロになってよかったなあ」と。









