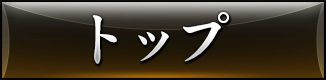





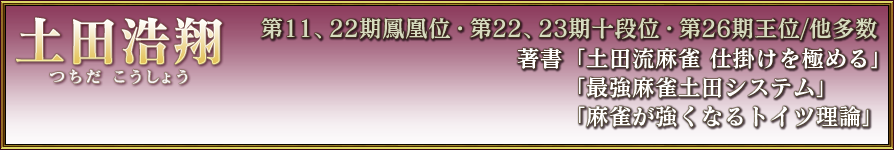
第四十九打「究極のテンパイとらず」 2020/11/11
テンパイとらずという手法があります。
その手法をとる理由は、おおよそ5つ。
(1) テンパイの形が悪い
(2) 打点をアップさせたい
(3) リーチをかけずにアガリたい
(4) フリテンテンパイを避けたい
(5) 不調を打破するきっかけを作りたい
(1)の例としては
こんな形のテンパイになったとき、カン![]() というアガリにくい待ちを避けて、テンパイとらずの
というアガリにくい待ちを避けて、テンパイとらずの![]() 切りとします。
切りとします。
このイーシャンテンに戻しておけば、カン![]() 以上の待ちに変化する牌は、
以上の待ちに変化する牌は、![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 、
、![]()
![]() 、
、![]()
![]() の10種類もあります。(
の10種類もあります。(![]() はフリテンになるので一応除外しておきます)
はフリテンになるので一応除外しておきます)
(2)の例としては
極端な例になったかもしれませんが、![]() を切ってリーチをかけ、
を切ってリーチをかけ、![]() でもツモって裏ドラが乗ればいいやと考える選択より、
でもツモって裏ドラが乗ればいいやと考える選択より、![]() さえトイツ落としできれば、高打点に近づくテンパイとらずになるはずです。
さえトイツ落としできれば、高打点に近づくテンパイとらずになるはずです。
こんな例もあるでしょう。
![]() とドラ
とドラ![]() があるので、このままリーチをかけてもツモればマンガンありますし、親であれば出アガリでも7700なので、即リーチかける手もありますが、ツモ
があるので、このままリーチをかけてもツモればマンガンありますし、親であれば出アガリでも7700なので、即リーチかける手もありますが、ツモ![]() やツモ
やツモ![]() への期待をこめて、テンパイとらずの
への期待をこめて、テンパイとらずの![]() 切りとしても面白いのです。
切りとしても面白いのです。
もっとも、この打点アップのテンパイとらず策には、ある程度巡目の早さも必要とされるケースも多く、11巡目を過ぎてしまうと、その変化も期待しにくくなるでしょう。
(3)の例としては
リーチをかけずにアガリたい局面というのは確かにあります。
こんな役無しノミ手テンパイになったのが9巡目くらいまでの早い段階であったなら、テンパイとらずの![]() トイツ落としか、要牌となりやすい
トイツ落としか、要牌となりやすい![]() がまだ切っていける巡目であれば、ピンフを確定させられるトイツ落としを考えてもいいでしょう。
がまだ切っていける巡目であれば、ピンフを確定させられるトイツ落としを考えてもいいでしょう。
ただし、![]() がドラなので、その
がドラなので、その![]() を引いてしまったときにローリングしやすくなる
を引いてしまったときにローリングしやすくなる![]() トイツ落としが賢明かもしれません。
トイツ落としが賢明かもしれません。
もうひとつ挙げておくとすれば
何らかの事情によって、リーチをかけたくないなと考えるときは、![]() をトイツ落とししてタンヤオ手とし、
をトイツ落とししてタンヤオ手とし、![]() のチーに備えておくテンパイとらずもあるでしょう。
のチーに備えておくテンパイとらずもあるでしょう。
(4)や(5)については、例を挙げるまでもなく、テンパイをとりたくないという強い意思が働くので、その時々でテンパイとらずの判断をしていくことになるでしょう。
ここまではメンゼンの話で進めてきましたが、本題はここからです。
皆さんは、仕掛け手で2フーロしたとき、しかもその手がマンガンだったとき、テンパイとらずした経験ありますか?
そんなことって??と思われて当然です。
メンゼンであればまだしも、いくら待ち方に不服があるからと言って、2フーロして手牌は7枚しか持っていないのに、マンガンのテンパイをとらないなんてこと、あり得ないと考えるのは正常な思考です。
でも私は敢えて提言します。
マンガンやハネ満手は、誰だってアガリたいはずです。
にもかかわらず、テンパイしたからと、ちょっと不安の残る待ち方であっても、もしかしたら…という気持ちが強くなり、ついテンパイをとってしまいアガリを逃す、そんなプレーに陥っていませんか?
マンガンやハネ満をアガらせるためには、その待ち方をイチかバチかの待ちに自ら追い込むのではなく、ちょっと味付けする時間を作って、アガリに近づける手法(テンパイとらず)が求められるのです。
では具体的にどんな手牌でその手法を使えばいいのか、例を挙げていきましょう。
西家で2フーロした手牌です。
![]() も
も![]() も生牌です。
も生牌です。
巡目が11巡目を過ぎていたら、アガリが不透明なシャンポンテンパイをとる手もありますが、マンガンをモノにしたいと考えるならば、テンパイとらずの![]() 切り、これが面白い一手になるはずです。
切り、これが面白い一手になるはずです。
トイトイのハネ満を狙うわけではありません。もしそんな大それたことを考えるのであれば、その前に![]() か
か![]() でアガっていることになりますから、少し欲張りすぎかもしれませんね。
でアガっていることになりますから、少し欲張りすぎかもしれませんね。
このテンパイとらずの狙いは、![]()
![]() です。
です。
平面的に考えて、![]() と
と![]() はあと2枚ずつありますが、
はあと2枚ずつありますが、![]() が1枚あるぶん、シャンポン待ちの出アガリは実質3枚しか期待できないかもしれません。
が1枚あるぶん、シャンポン待ちの出アガリは実質3枚しか期待できないかもしれません。
対する![]()
![]() は8枚ありますから、自力で1枚引くことができれば、
は8枚ありますから、自力で1枚引くことができれば、![]()
![]() のシャンポンテンパイよりアガリが近づくことは容易におわかりいただけるはずなのです。
のシャンポンテンパイよりアガリが近づくことは容易におわかりいただけるはずなのです。
問題があるとすれば、![]()
![]() を引いてくる確率と、
を引いてくる確率と、![]()
![]() のシャンポンテンパイがそのままアガれる確率との比較で、まだ引いてない
のシャンポンテンパイがそのままアガれる確率との比較で、まだ引いてない![]()
![]() のほうが分が悪いと考えてしまうことです。
のほうが分が悪いと考えてしまうことです。
だから、現実にテンパイがとれている![]()
![]() のシャンポンのほうが<得>だと考え、2フーロしてテンパイとらずなどナンセンスという結論に至るのでしょう。
のシャンポンのほうが<得>だと考え、2フーロしてテンパイとらずなどナンセンスという結論に至るのでしょう。
ですから、賢明なる皆さんには、2フーロマンガン手牌のテンパイとらず手法の経験値を上げて欲しいと強く思います。
ではこの手牌はどうでしょう。
南家の河 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
西家の河 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
北家の河 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
早くも6巡目にテンパイ。
親満が確定しています。
シャンポンにとってから![]()
![]() 引きでの変化を狙うのか、カン
引きでの変化を狙うのか、カン![]() にとってから
にとってから![]()
![]() 引きでの変化を狙うのか二者択一。
引きでの変化を狙うのか二者択一。
と普通は考えるものですが、上目、下目への伸びを両方残す![]() 切りのテンパイとらずという手もあります。
切りのテンパイとらずという手もあります。
![]() を1枚外すと手牌はこうなります。
を1枚外すと手牌はこうなります。
場況を見ると、南家の2巡目の![]() 、西家の2巡目の
、西家の2巡目の![]() が目につきます。
が目につきます。
つまり、![]() が両者の手牌に組み込まれていない可能性が高く、上のテンパイとらずから
が両者の手牌に組み込まれていない可能性が高く、上のテンパイとらずから![]() を引いてカン
を引いてカン![]() 待ちになったとしても、アガリが近づくことになります。
待ちになったとしても、アガリが近づくことになります。
もちろん、![]() から先に引ければ
から先に引ければ![]()
![]() のリャンメン待ちになりますから文句なしのテンパイとなります。
のリャンメン待ちになりますから文句なしのテンパイとなります。
であれば、最初から![]() 切りの
切りの![]()
![]() のシャンポンテンパイをとっておいても良いのでは?と考える人も多いでしょう。
のシャンポンテンパイをとっておいても良いのでは?と考える人も多いでしょう。
でも北家の第1打![]() も気になります。
も気になります。
北家が![]() を持ってない確率が高いので、マンズの下目が伸びる可能性も否定できないと考え、そのキー牌となる
を持ってない確率が高いので、マンズの下目が伸びる可能性も否定できないと考え、そのキー牌となる![]() をも残すという一石二鳥作戦をとります。
をも残すという一石二鳥作戦をとります。
どちらが伸びるのかと云えば、マンズの上目のほうがいいとなり、そうなったとき、先に![]() を切って、テンパイしたときに
を切って、テンパイしたときに![]() を放すと、親の手出しが
を放すと、親の手出しが![]() →
→![]() となりますから、カン
となりますから、カン![]() 待ち、
待ち、![]()
![]() 待ち共に子方の目から盲点になる寸法です。
待ち共に子方の目から盲点になる寸法です。
2フーロしてマンガンテンパイした手牌をイーシャンテンに戻すことは、かなり<損>な手法に見えるかもしれません。
しかしながら、アガリたい手牌ほど、イチかバチかの待ちは避けて、アガリ易い待ちに作り替える勇気がもてれば、文字通り『損して得を取る』という結果になりやすいので、是非、実戦で試されてはいかがでしょうか。









