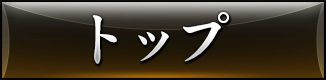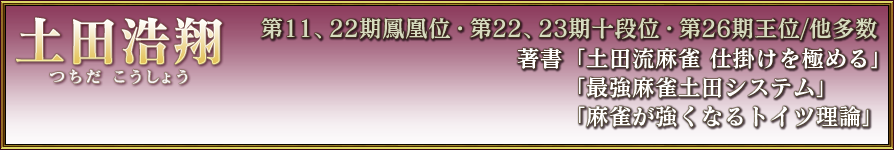
第五十八打「読みを外す手順」 2023/04/12
好むと好まざるとにかかわらず、打ち手は相手の河を見ながら選択していきます。
ましてや、仕掛け手やリーチとなれば、なんとか放銃しないようにと、河を読みながら、あるいは何かを感じながら選択していくものです。
東2局、親からリーチが入りました。
親の河はこうなっています(ドラ![]()
![]() と
と![]() はツモ切り)
はツモ切り)
このリーチを読む側に立てば
![]() のツモ切り
のツモ切り
![]() の手出し
の手出し
![]() を手出ししてのリーチ
を手出ししてのリーチ
この3点に読みが働きます。
まずは![]() のツモ切りについて。
のツモ切りについて。
例外はありますが、序盤の心牌<5>切りの多くは、手牌に<23>や<78>があって、早めにテンパイしそうなので、<5>を手元に置いて<2345>や<5678>という四連形に期待しなくていいケースです。
つまり、この河で言えば、親の手牌に![]()
![]() か
か![]()
![]() というリャンメン形が6巡目の時点で存在しているのではないか?という読みが働くのです。
というリャンメン形が6巡目の時点で存在しているのではないか?という読みが働くのです。
そしてその読みから、ピンズで危険なスジは、![]()
![]() と
と![]()
![]() ということになり、ドラが
ということになり、ドラが![]() ゆえ、
ゆえ、![]()
![]() は特に危険視していい待ちに浮上するのです。
は特に危険視していい待ちに浮上するのです。
次に![]() の手出しについて。
の手出しについて。
4巡目に![]() が切られているので、マンズは手出しされた
が切られているので、マンズは手出しされた![]() の周辺が必要だった可能性が高く、複合形で持っていたか、優れた孤立牌としてキープしていたかのどちらかで、後者のケースは、リーチの待ちに関連していないため、前者だけに絞って読みを働かさなければなりません。
の周辺が必要だった可能性が高く、複合形で持っていたか、優れた孤立牌としてキープしていたかのどちらかで、後者のケースは、リーチの待ちに関連していないため、前者だけに絞って読みを働かさなければなりません。
考えられる形としては
A ![]()
![]()
![]()
B ![]()
![]()
![]()
C ![]()
![]()
![]()
D ![]()
![]()
![]()
E ![]()
![]()
![]()
F ![]()
![]()
![]()
G ![]()
![]()
![]()
H ![]()
![]()
![]()
I ![]()
![]()
この9パターンのうち、DFGHは複合形が雀頭になるケースなので、![]() が孤立牌だったケース同様、読みの対象にはなりません。
が孤立牌だったケース同様、読みの対象にはなりません。
Iは![]()
![]() に
に![]() を引いてリャンメン形になったケースなので、
を引いてリャンメン形になったケースなので、![]()
![]() 待ちは読みの対象になります。
待ちは読みの対象になります。
Aは![]()
![]() 待ち、Bは
待ち、Bは![]()
![]() 待ち。
待ち。
Cはカン![]() 待ち、Eはカン
待ち、Eはカン![]() 待ちになりますから、AやBのケースと待ちが被るため、危ない牌は、
待ちになりますから、AやBのケースと待ちが被るため、危ない牌は、![]()
![]()
![]()
![]() と読めるわけです。
と読めるわけです。
Iのケースの![]() を加えれば、マンズの危険スジは3通りに絞れることになります。
を加えれば、マンズの危険スジは3通りに絞れることになります。
最後にリーチ表示牌![]() の手出しについて。
の手出しについて。
![]()
![]() というシュンツ作りには欠かせない牌たちの後に出てくるということは、とても大切な牌だったということに他なりません。
というシュンツ作りには欠かせない牌たちの後に出てくるということは、とても大切な牌だったということに他なりません。
ましてや親のリーチですから、寸分の隙なく手組みしていく段取りを想像すると、この![]() は、とてつもなく重要な牌だったということになります。
は、とてつもなく重要な牌だったということになります。
考えられる形としては
A ![]()
![]()
![]()
B ![]()
![]()
![]()
C ![]()
![]()
![]()
D ![]()
![]()
![]()
E ![]()
![]()
![]()
F ![]()
![]()
![]()
G ![]()
![]()
![]()
H ![]()
![]()
![]()
I ![]()
![]()
![]()
この9パターンのうち、Iは除外されます。
なぜなら、5巡目に![]() を切っていますから、まさかフリテンカンチャンリーチとはしないでしょうから。
を切っていますから、まさかフリテンカンチャンリーチとはしないでしょうから。
残りの8パターンのうち、EFGは、複合形が雀頭になったケースなので読みの対象にはなりません。
Hについては、![]() を期待してのシャンポンリーチはよくあるケースなのでマークが必要になります。
を期待してのシャンポンリーチはよくあるケースなのでマークが必要になります。
このケースでは、リーチ後に![]() が通っても安心して
が通っても安心して![]() は切らないほうがいいでしょう。
は切らないほうがいいでしょう。
Aは![]()
![]() 待ち、Bは
待ち、Bは![]()
![]() 待ち。
待ち。
Cはカン![]() 待ち、Dはカン
待ち、Dはカン![]() 待ちになりますから、AやBのケースと待ちが被るため、危ない牌は、
待ちになりますから、AやBのケースと待ちが被るため、危ない牌は、![]()
![]()
![]()
![]() と読めるわけです。
と読めるわけです。
すべてを整理すると
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この13種類の牌たちが、親のリーチに当たる可能性が高いということになります。
基本的には、リーチ表示牌の周辺が一番危なくて、次にリーチの一手前に手出しされた牌の周辺が危ないので、この親のリーチに危険な色は、ソーズ→マンズ→ピンズの順になると考えます。
ただし、ドラ周りは決め打ちしやすいので、この局のようにドラが![]() の場合
の場合
![]()
![]()
![]() からの
からの![]() 切り
切り
![]()
![]()
![]() からの
からの![]() 切り
切り
などは序盤に切り出せる牌なので、いつだって読みの中心に据えておくことです。
そしてここからが今回のテーマである読みを外す話になります。
リーチを受けた8巡目の南家の手牌です。
5巡目に親は![]() を手出しし、その後
を手出しし、その後![]() ツモ切り、
ツモ切り、![]() を手出しした後、
を手出しした後、![]() を手出ししてリーチしてきたので、南家の読みとしては、
を手出ししてリーチしてきたので、南家の読みとしては、![]() は孤立牌の処理と考え、雀頭候補の
は孤立牌の処理と考え、雀頭候補の![]() と
と![]() を比べると
を比べると![]() はロンされにくい牌のひとつだったため、
はロンされにくい牌のひとつだったため、![]() の対子を落とそうとしたところ
の対子を落とそうとしたところ
「ロン」
親の手牌が開けられたのです。
「えっ?![]() の周りの牌が無い」
の周りの牌が無い」
「えっ?手牌と無関係な![]() がなぜ・・・?」
がなぜ・・・?」
南家は茫然自失となってしまいました。
ここで親の巧妙な手順を再現しましょう。
配牌
1巡目 打![]()
2巡目 ツモ![]() 打
打![]()
3巡目 ツモ![]() 打
打![]()
4巡目 ツモ![]() 打
打![]()
5巡目 ツモ![]() 打
打![]()
6巡目 ツモ![]() 打
打![]()
7巡目 ツモ![]() 打
打![]()
8巡目 ツモ![]() 打
打![]() リーチ
リーチ
この5巡目の![]() 切りについて再現してみましょうか。
切りについて再現してみましょうか。
手牌にあるトイツ牌はすべて生牌です。
親であることを踏まえれば、![]()
![]()
![]() の暗刻にも備えたテンパイ効率重視で打つのが標準で、この
の暗刻にも備えたテンパイ効率重視で打つのが標準で、この![]() はツモ切りする打ち手が多数派だと思われます。
はツモ切りする打ち手が多数派だと思われます。
ところがこの親は、もし![]()
![]() 待ちになった場合、早めに
待ちになった場合、早めに![]() を切っておいたほうが
を切っておいたほうが![]() を狙えるかなと考え、テンパイ効率には目を瞑ってこの5巡目の河に
を狙えるかなと考え、テンパイ効率には目を瞑ってこの5巡目の河に![]() を見せておいたのです。
を見せておいたのです。
もちろん、![]() に
に![]() や
や![]() がくっつけば、この段階で不安定形の
がくっつけば、この段階で不安定形の![]()
![]()
![]() という複合形とリャンメン形を交換できるメリットもあったので、相手の読みを外す効果と一石二鳥の
という複合形とリャンメン形を交換できるメリットもあったので、相手の読みを外す効果と一石二鳥の![]() 切りと相成ったのです。
切りと相成ったのです。
7巡目、ここもポイントとなる選択です。
親はイーシャンテンとなり![]() を切ったのですが、これは明らかに
を切ったのですが、これは明らかに![]() を引き出すためのひと工夫です。
を引き出すためのひと工夫です。
![]() より
より![]() のほうが重要だった、そう相手に読ませるための
のほうが重要だった、そう相手に読ませるための![]() の引きつけです。
の引きつけです。
打点ということを考えれば、![]() にもう1枚
にもう1枚![]() を引いて
を引いて![]()
![]() を放せば
を放せば
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
こんなテンパイも想定できた手牌でしたが、![]()
![]() 待ちでリーチをかけられる効果を優先して、親は
待ちでリーチをかけられる効果を優先して、親は![]() を切ったのです。
を切ったのです。
もっとも、入り目の問題があって、![]()
![]() から埋まらずに
から埋まらずに![]()
![]() から埋まることも当然考えられ、親の読み外しも徒労に終わる公算もありましたが、親は2分の1の確率に賭けて
から埋まることも当然考えられ、親の読み外しも徒労に終わる公算もありましたが、親は2分の1の確率に賭けて![]() をテンパイまで引っ張ったのです。
をテンパイまで引っ張ったのです。
テンパイ効率ですとか、完全イーシャンテンですとか、とかくテンパイ優先の考え方がもてはやされていますが、私は<アガリ効率>を優先したほうが成績は安定すると思っています。
そのためには、相手の読みを外す河作りは欠かせないものと考えています。
もちろん、相手によって使い分けてもいいと思います。
読まずにガンガン攻めてくる相手には、テンパイ効率重視、複合形重視でいいでしょう。
ただ、読みを駆使する相手には、その読みを外していく手順と河作りが必要なのではないでしょうか。