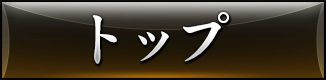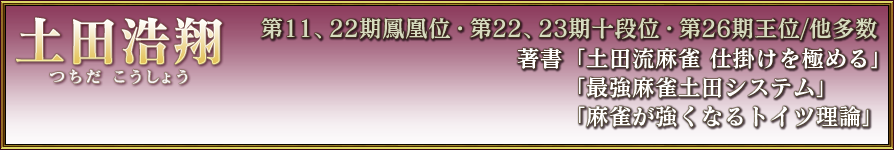
第六十打「二兎は追わず」 2023/10/18
こんな手牌がやってきたら、あなたはどんな選択をしますか?
東4局 北家 5巡目 原点からマイナス3000点
場には、![]() と
と![]() が1枚ずつ出ています。
が1枚ずつ出ています。
![]() はドラ表示牌に見えているだけです。
はドラ表示牌に見えているだけです。
手中のトイツ牌はすべて生牌です。
打![]()
これが多数派かなと思われます。
このように![]() さえ切っておけば、手牌はタンヤオ牌だらけになり、
さえ切っておけば、手牌はタンヤオ牌だらけになり、
早めに![]() が引けたり鳴けたりできたならば、この手牌のマンガン成就はより現実的なものになるでしょう。
が引けたり鳴けたりできたならば、この手牌のマンガン成就はより現実的なものになるでしょう。
もちろん、最高のプランとなるドラ![]() を引いての七対子テンパイ。
を引いての七対子テンパイ。
場況に従って、![]() 待ちか
待ちか![]() 待ちにすれば、出アガリでもヤミテンでハネ満、リーチをかければ倍満の大物手となります。
待ちにすれば、出アガリでもヤミテンでハネ満、リーチをかければ倍満の大物手となります。
ですから、最初の手牌から1枚切れの![]() を切って、タンヤオ手(喰いタン含む)と七対子の『二兎を追う』選択は正しいとする論調が多いのは事実です。
を切って、タンヤオ手(喰いタン含む)と七対子の『二兎を追う』選択は正しいとする論調が多いのは事実です。
ところがこの手牌を考えるときに、とても大事な1点が見落とされています。
それは、<自力>で進めるのか<他力>を利用するのかという選択です。
私は、麻雀を打つうえで大切なことは<運>とどう向き合っていくのか?という点を見落としてはならないということだと考えています。
<運>をどうやって引き寄せるのか?
答えは簡単です。
(一) アガりたい欲を棄てる
(二) メンゼンで手を進める
(三) 余計な動き(一発消しや海底ずらし)はしない
(四) リーチはアガリに近づけた最終形でかける
(五) 放銃を悪ととらえない
細分化するともう少しありますが、(一)〜(五)を実践するだけで<運>は引き寄せられます。
だったら仕掛けないのか?
メンゼンだけで打つのか?
こんな疑問を抱く方もいらっしゃるでしょうが、仕掛けるべき手は仕掛ける、これが答えになります。
えっ?!なんか言っていることが分からない。
その疑問にもお答えしておきましょう。
仕掛けるべき手とは2つあって
(1) 3ハン以上が見込める手
(2) 初動から6〜7巡以内にアガれそうな手
この2つに該当する場合は、本手の仕掛けとなり<運>は逃げていきません。
(1)については、高打点が見込めるので、メンゼンのときと同じで、たとえアガリまで到達しなくても<運>は貯まります。
(2)については、速攻が見込める手牌ですから、アガり切ることが重要なテーマで、空振りに終わると<運>が少し離れるので全力投球(オリ無し)が求められます。
仕掛けは、麻雀を打つスキルの中でもっとも難しい分野なので、安易に<他力>を利用しないほうがいいのです。
冒頭の手牌に戻りましょう。
東4局 北家 5巡目 原点からマイナス3000点
シュンツ含みの手のリャンシャンテン。
七対子のイーシャンテン。
<運>を引き寄せるビッグチャンス到来。
となると、メンゼンでしかアガれない七対子に向かったほうが良いかも、と考えられるようになればしめたものです。
ちょっとキャリアを積んで、効率や牌理にも強くなってくると、『二兎を追う』便利さに気づいてしまいます。
5巡目という早さからも『二兎を追う』にはちょうどいい言い訳ができます。
ですからさほど迷うことなく![]() 切りを選択してしまうのですが・・・
切りを選択してしまうのですが・・・
「決断は早ければ早いほど強くなれる」
この言葉を忘れて欲しくありません。
<自力>でいくのか<他力>を利用するのかの決断も早いほうがいいんです。
しかもビッグチャンス到来。
人間は弱いもので、チャンスが来ていると感じると慎重になってしまいます。
するとどうなるのか?
『水も漏らさぬ構えでいかなくては』
という思考に陥って『二兎を追う』時には『三兎を追う』選択をしてしまいます。
この手牌はメンゼンでいこう!
という決断があればあなたは強くなれます。
打![]()
手牌をよく見てみましょう。
![]() トイツのスジ牌
トイツのスジ牌![]()
![]() トイツのスジ牌
トイツのスジ牌![]()
この2種は重なりやすい性質があります。
それに対して、七対子手牌では、よほど場況の味方がないかぎり、尖張牌(3と7)は他の数牌より重なりにくい性質があるため
![]() ・
・![]() ・
・![]() ・
・![]()
ドラ![]() はまだ切らない巡目であるならば
はまだ切らない巡目であるならば![]() 切りの一手となるのです。
切りの一手となるのです。
七対子が苦手な人にとってこの決断は難行苦行の世界に入ることになりますから、無理におすすめはできません。
ただし、偶然テンパイしてしまうとき以外は、1ミリも七対子のことは考えずに打っていくべきです。
そして、七対子に向かわないわけですから、もうひとつの決断、メンゼンでいくのか仕掛けていくのかという選択をこの巡目でしておくことが肝要です。
一番あってはいけない考え方は
「もしかしたら・・・うまくいくかも」という甘〜い甘〜い希望を抱くことです。
この手牌を自力で仕上げられると見通せたなら、仕掛けの誘惑に負けず、徹底してメンゼンを貫き通したほうがいいでしょう。
その前提として、「アガれなくても仕方ない」という腹のくくりが必要です。
どうしてもアガりたいから仕掛けていく、そう決断したとしても、では初動はどこからいこうか、打点はどこを目標にしようか、という更なる決断をしておくべきです。
他力を利用するのですから、フィニッシュまで他力でいく、つまり「ロン」でアガることを目標に仕掛け手順の設計をしたほうがいいのです。
決断をしても、途中で想定外の牌を引いてしまったら?
たとえば
う〜ん、と首を傾けながら![]() を切って、
を切って、![]() や
や![]() が出てきたらポンして軌道修正しようかなと考えるのは、臨機応変な対応ではなく、ただの優柔不断です。
が出てきたらポンして軌道修正しようかなと考えるのは、臨機応変な対応ではなく、ただの優柔不断です。
自分ではうまく方向転換しているつもりでも、決断したことへのリスペクトが弱すぎで、強さを求める道は険しくなるでしょう。
![]() や
や![]() 、
、![]() や
や![]() 、そして
、そして![]() が暗刻になったときも同じです。
が暗刻になったときも同じです。
最初から、この手牌はトイトイで仕上げるんだという決断があったなら、暗刻が増えることは大歓迎でしょうが、ふとした出来事だったなら、ツモ切りして七対子の道を進んでいくべきです。
今回の手牌に限らず、『二兎を追う』手順は一見すると柔軟な対応に見えますし、打っていて安心感もあるでしょうが、その習慣が付いてしまうと、強くなる道が閉ざされていきますし、<運>も貯まらなくなります。
世の風潮に惑わされることなく、できるかぎり決断を早めにして、『二兎を追わない』打ち手になって欲しいなと期待しています。