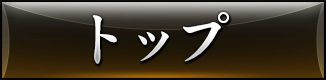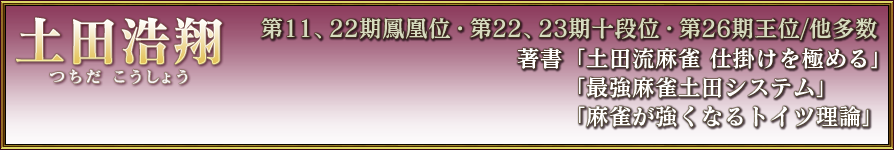
第六十一打「6巡目までの道」 2024/02/16
河(捨て牌)は三段に分けて並べます。
その一段目(6巡目まで)が序盤戦。
二段目(12巡目まで)が中盤戦。
そして三段目(18巡目まで)が終盤戦。
この3つの分類のうち、もっとも重要視されるべきものは序盤戦だと考えています。
なぜなら、序盤戦は他家からのプレッシャーがかかりにくく、自由に打っていける局面だからです。
自由に打てるイコール打ち手の麻雀能力が如何なく発揮できるということになり、与えられた手牌に対しての思考が丸裸になります。
極論すれば、まだアガリが発生しにくい6巡目までの<手筋>やそれに伴う<手順>を見れば、その打ち手の麻雀能力がどのレベルにあるのかが判明してしまうのです。
ですから、序盤への取り組みをしっかりしていけば、自ずと麻雀能力はアップするはずです。
では具体的に手牌を追ってみましょう。
東1局の親の配牌です。
さて第1打には?
![]() or
or![]() と答えた人が多いでしょうか。
と答えた人が多いでしょうか。
令和の時代になって顕著に見られる字牌からの切り出し。
とくに東場での子方は判で押したように![]() を第1打にしています。
を第1打にしています。
その理由としては、親がダブ東を重ねる前に切っておきたいというもので、理に適っているのでしょう。
![]() を持っていないときは、よほど何らかの手役で必要でない限り、
を持っていないときは、よほど何らかの手役で必要でない限り、![]()
![]()
![]() のどれかが第1打となります。
のどれかが第1打となります。
その理由としては、たとえこれらの役牌をトイツで持っていたとしても、手牌が整わない第1打時点ではポンしてこないだろうという、これまた理に適ったものになっています。
連風牌はポンできれば2ハンになりますから、雀頭に据えてもいいという考えには至りませんが、1ハンの役牌であれば、雀頭でもいいかなという手組みになりやすいため、第1〜3打あたりでのポンは自重するだろうという読みが働いています。
ですから、親のこの配牌から![]() を第1打にするのは理に適った1打に思えるのでしょう。
を第1打にするのは理に適った1打に思えるのでしょう。
何巡か経ってから![]() を切ると、相手が速攻をかけてもいい形に変化していて、ポンしやすいタイミングになっているかも知れず、第1打がベストという判断です。
を切ると、相手が速攻をかけてもいい形に変化していて、ポンしやすいタイミングになっているかも知れず、第1打がベストという判断です。
![]() ではなく、
ではなく、![]() を第1打に選択する理由としては、自身で
を第1打に選択する理由としては、自身で![]() を重ねて、アガリに向かっていく際の武器としてもいいかなというもので、一見するとタンヤオでまとまりそうに見える手牌でも、
を重ねて、アガリに向かっていく際の武器としてもいいかなというもので、一見するとタンヤオでまとまりそうに見える手牌でも、![]() さえ重ねられれば、アガリへの速度感が増すと考えているのです。
さえ重ねられれば、アガリへの速度感が増すと考えているのです。
いずれにしても、数牌より字牌を先に整理したほうが得なのでは?と考える打ち手は多数派を形成しているようです。
私の第1打は![]() 。
。
![]() には
には![]() と
と![]() が引ければ組み合わせが増える利点があり、
が引ければ組み合わせが増える利点があり、![]() をあと2枚引いて組み合わせを作るより効率的です。
をあと2枚引いて組み合わせを作るより効率的です。
その利は承知のうえで、自信をもって![]() を第1打にすることをオススメします。
を第1打にすることをオススメします。
![]() を第1打に選ぶ理由は5つあります。
を第1打に選ぶ理由は5つあります。
1、ドラが![]() であり、
であり、![]() や
や![]() を引いてきても
を引いてきても![]() でカバーできるため、相手の待ちになるかもしれない
でカバーできるため、相手の待ちになるかもしれない![]() を1巡でも早く切っておきたい
を1巡でも早く切っておきたい
2、組み合わせとしては、この1巡目の段階では、マンズ・ピンズ・ソーズ1組ずつプラスどの色で作るかは見えておらず、![]()
![]()
![]() が残り1組を作るキー牌となっているため、孤立牌の
が残り1組を作るキー牌となっているため、孤立牌の![]() は使い勝手が悪いという判断
は使い勝手が悪いという判断
3、![]() は組み合わせの4組目になる可能性があるため、まだ1巡目では切らない
は組み合わせの4組目になる可能性があるため、まだ1巡目では切らない
4、![]() は数巡のちに安全牌となる可能性が高く、またトイツになれば雀頭として機能し、トイツの
は数巡のちに安全牌となる可能性が高く、またトイツになれば雀頭として機能し、トイツの![]() を1枚外して手幅を広げられる
を1枚外して手幅を広げられる
5、数牌のもうひとつの孤立牌![]() は、
は、![]() さえ引ければ
さえ引ければ![]()
![]()
![]() というリャンカン形となり、4組目の組み合わせができる有力な形となる
というリャンカン形となり、4組目の組み合わせができる有力な形となる
東1局の親の配牌に戻ります。
![]()
![]() と
と![]()
![]() は分けて見ています。
は分けて見ています。
もちろん、![]() をあっさり引ければ好形になりますがドラ
をあっさり引ければ好形になりますがドラ![]() を先に引くと組み合わせが
を先に引くと組み合わせが![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]() に分かれますね。
に分かれますね。
ピンズにも似たようなことが言えます。
![]() をあっさり引ければ
をあっさり引ければ![]()
![]()
![]()
![]() という好形になるので、ピンズでの組み合わせが2組できる可能性は高まります。
という好形になるので、ピンズでの組み合わせが2組できる可能性は高まります。
ただ、この配牌時点では![]()
![]() と
と![]() は切り離してみておいたほうが実戦的で、
は切り離してみておいたほうが実戦的で、![]() を先に引けないことも想定しつつ、
を先に引けないことも想定しつつ、![]() の見切り時を考慮しておかなければなりません。
の見切り時を考慮しておかなければなりません。
ソーズ部分は一番わかりやすく、![]()
![]() というリャンメン形と孤立牌
というリャンメン形と孤立牌![]() に何がくっついてくるのか?といういたってシンプルな組み合わせ作りになるはずです。
に何がくっついてくるのか?といういたってシンプルな組み合わせ作りになるはずです。
ベストは![]() 引きで、
引きで、![]()
![]()
![]()
![]() の4連形になれば、ソーズで2組作ることは十分可能となります。
の4連形になれば、ソーズで2組作ることは十分可能となります。
第1打![]() とすると手牌はこうなります。
とすると手牌はこうなります。
第2ツモ ![]() 〜
〜![]()
打牌 ![]()
第2ツモ ![]() 〜
〜![]()
打牌 ![]()
第2ツモ ![]() 〜
〜![]()
打牌 ![]()
第2ツモ ![]()
打牌 ![]()
第2ツモ ![]()
打牌 ![]()
第2ツモで字牌が重なったときだけ数牌を選ぶことになり、数牌の有効牌(もしくはそれに準ずるもの)が引けた場合は![]() 切りとなります。
切りとなります。
![]()
![]()
![]() はツモ切りとなり、
はツモ切りとなり、![]()
![]()
![]()
![]()
![]() を引いたときは、役牌の場合は
を引いたときは、役牌の場合は![]() 切り、
切り、![]() や
や![]() の場合はすでに場に出ているほうを手元に残します(安全牌化しやすいため)。
の場合はすでに場に出ているほうを手元に残します(安全牌化しやすいため)。
3巡目以降は、子方のリーチが近づいてくるため、よほどの好形に変化しないかぎり、安全牌化した字牌は1枚手元に置いておきます。
![]()
![]()
![]() という急所が引けてこの形になったならば、開局の親ということも追い風となり、安全牌は置かずに勝負していきます。
という急所が引けてこの形になったならば、開局の親ということも追い風となり、安全牌は置かずに勝負していきます。
そうでなくて、これくらいの進展であれば
安全牌の![]() は残しながら打っていきます。
は残しながら打っていきます。
この手牌の急所となっているマンズ部分
![]()
![]()
![]()
![]()
6巡目までにここがアガリやすい形に変化しないときは、トイツの![]() を6巡目に手放しておいたほうがいいでしょう。
を6巡目に手放しておいたほうがいいでしょう。
![]() や
や![]() が場に2枚以上出ていても、急所が片付いていない危機感をもって、ドラのとなりで相手の欲しそうな
が場に2枚以上出ていても、急所が片付いていない危機感をもって、ドラのとなりで相手の欲しそうな![]() をいつまでもトイツで引っ張らないようにすることです。
をいつまでもトイツで引っ張らないようにすることです。
巷にあふれる話としては、『![]() や
や![]() あるいは
あるいは![]()
![]() が引ければテンパイになるリャンシャンテンなのだから、まだ6巡目の親としては字牌を2枚も抱えるのは損だろう』
が引ければテンパイになるリャンシャンテンなのだから、まだ6巡目の親としては字牌を2枚も抱えるのは損だろう』
『このテンパイを逃してなるものか!
即リーチをかければ子方は平伏すだろう』
いわゆる『親なのだから』理論なのですが、麻雀能力をアップさせようと希望する打ち手は抱いてはならない理論です。
麻雀能力をアップさせるためには、次の3つの要素が求められます。
1、アガリに近づけて打つ能力
2、相手の早いリーチに対応できる能力
3、無駄なエネルギーを使わない能力
この3つの能力を高めるために、序盤戦の手の進め方が重要になってくるのです。
つまり、相手からのプレッシャーがかかっていない6巡目までに、その局の攻撃態勢や守備態勢を準備しておく必要があるのです。
第1打〜第6打までを研ぎ澄ませてみようではありませんか!