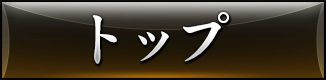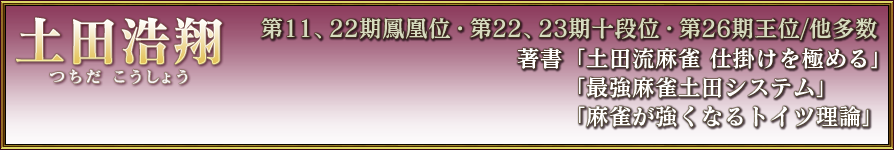
第六十五打「七対子と四暗刻」 2025/03/24
どんな役が好きですか?と問われれば、タンヤオ・ピンフ・三色と答えてしまう私がいますが、どんな役を作るのが好きですか?と問われたら、七対子と四暗刻と即答します。
タンヤオ・ピンフ・三色は持ち点に余裕があるときにはアガリまで望めるものの、持ち点が原点からマイナス1万点を超えると途端にテンパイ止まりになってしまいます。
つまり、タンヤオ・ピンフ・三色を成就させるためには持ち点の追い風が必要ということになるのです。
ところが七対子や四暗刻は、持ち点の多寡にかかわらずアガリまでの道が残されていて、ストライクゾーンの広い役となっています。
ですから私は「作る」ということであれば七対子や四暗刻作りが好みなのです。
ただ気をつけなければならないことがこの2つの役にはあって『天秤にかけてはならない』という決めゼリフがあります。
打ち手が陥りやすい『天秤病』。
三色と一気通貫、チャンタと混老頭、七対子と一盃口などは『天秤病』には罹らないのですが、七対子と四暗刻は『天秤にかけてはならない』役同士なのです。
なぜなら、トイツ候補の素材が違うからということに尽きます。
トイツは偶然増えたり、暗刻も偶然できると考えているかぎり、七対子や四暗刻作りに勤しむことはできません。
トイツを計画的に増やして七対子を成就させる、暗刻を計画的に増やして四暗刻を完成させる技術を身につけて欲しいのです。
A 東4局 西家 5巡目 原点からマイナス9000点
私の選択=![]() 切り
切り
原点からマイナス9000点という点棒状況からタンヤオ・ピンフへの道はこじ開けられないと考えます。
しかも七対子のイーシャンテンになったのですから点棒状況にマッチした方向でいきます。
七対子に向かう場合、![]()
![]()
![]()
![]() がトイツ候補となるわけですが、マンズの並びが一盃口形の
がトイツ候補となるわけですが、マンズの並びが一盃口形の![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() になっているため、
になっているため、![]() や
や![]() は引いてきやすい牌たちです。
は引いてきやすい牌たちです。
これは七対子を作っていくときの基本で、一盃口になろうとしている牌たちが重なりやすいというトイツ場らしいツモの流れを想定しています。
また![]() は
は![]() と比較すると、言わずもがなのスジトイツシステムで、
と比較すると、言わずもがなのスジトイツシステムで、![]() トイツのスジ牌
トイツのスジ牌![]() は
は![]() よりも重なりやすいというトイツ場ならではの山の積まれ方に則したものです。
よりも重なりやすいというトイツ場ならではの山の積まれ方に則したものです。
このシステムを応用するとマンズ部分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この![]() は
は![]() のスジに当たるので、一盃口形とのW効果が期待できるため、同じスジトイツの
のスジに当たるので、一盃口形とのW効果が期待できるため、同じスジトイツの![]() よりも重なりやすいという見立てができるのです。
よりも重なりやすいという見立てができるのです。
最近の打ち方を見ていると、Aの手牌から![]() をトイツ落とししてタンヤオに移行し、ポン材が出たら積極的に喰いタンに走っていく傾向にありますが…。
をトイツ落とししてタンヤオに移行し、ポン材が出たら積極的に喰いタンに走っていく傾向にありますが…。
喰うという行為は他力に頼る打法です。
メンゼンでイーシャンテンになった手牌を、リャンメン形を大事にしたいという安直な考えで喰っていく習慣をつけてしまうと、メンゼン力が落ち、強さも伴わなくなります。
ですからツモ![]() と来たワケをもう1度考え直してみるといいかなと思っています。
と来たワケをもう1度考え直してみるといいかなと思っています。
B 南1局 北家 5巡目 原点からマイナス10000点
(※![]() は1枚切れ、他は生牌)
は1枚切れ、他は生牌)
私の選択=![]() 切り
切り
尖張牌(3と7)が配牌に暗刻で入っていたり序盤で暗刻になったときには四暗刻のサインではないか?といつも考えます。
四暗刻をアガっている人の手牌をチェックしてみると気づけるのですが、80%以上の手牌に尖張牌の暗刻が組み込まれています。
この手牌もまさにそれ。
オタ風の![]() が暗刻でドラも赤も無い手牌ですから、この5巡目のツモ
が暗刻でドラも赤も無い手牌ですから、この5巡目のツモ![]() は四暗刻への道が開けた瞬間と捉え、もうあとは四暗刻手順を踏んでいくだけです。
は四暗刻への道が開けた瞬間と捉え、もうあとは四暗刻手順を踏んでいくだけです。
四暗刻手順の肝は<生牌>残し
七対子手順の肝は<1枚切れ>残し
この違いを覚えておくと四暗刻や七対子の産出量が増えるはずです。
四暗刻が完成するときに出現する尖張牌の暗刻(![]() )はすでにあるわけですから、シュンツ手のキー牌である
)はすでにあるわけですから、シュンツ手のキー牌である![]()
![]() から処理していきます。
から処理していきます。
まずはドラそばの![]() から。
から。
次に![]() を処理し、その次は1枚切れの
を処理し、その次は1枚切れの![]() になります。
になります。
四暗刻手順の肝は<生牌>残しとしたのは、とてもわかりやすい理由からで、ひとつの牌が3つ揃う確率は1枚切れの牌より生牌のほうが断然優位だからです。
七対子は2枚揃えばいいわけですから、たとえば中盤(7巡目〜)以降は場に1枚出ている1・9・字牌が重なってきやすい利点を生かせばいいのです。
ところが四暗刻作りは違います。
残りの山に眠っているかどうかは賭けになりますが、1枚切れの![]() より生牌の
より生牌の![]() を残したほうが暗刻を増やしやすくなるのです。
を残したほうが暗刻を増やしやすくなるのです。
仮にBの手牌が10巡目に次のようなイーシャンテンになったとしましょう。
![]() と
と![]() が生牌、
が生牌、![]() は1枚切れです。
は1枚切れです。
こんなとき2枚目の![]() が出るとポンしてトイトイのテンパイを取る人がいます。
が出るとポンしてトイトイのテンパイを取る人がいます。
2枚目ですから当たり前のようにポンの声を発するわけですが、四暗刻手順で打っていたのにひとつ暗刻になる可能性が無くなったくらいで諦めるのはもったいない話です。
![]() が無くなったって
が無くなったって![]() と
と![]() があるではないですか!
があるではないですか!
そんな都合よく自分のツモ筋に![]() と
と![]() がいてくれるわけないでしょ、と考えるごくごく普通の感覚があなたの四暗刻産出量を減らしていることにそろそろお気づきになられても…。
がいてくれるわけないでしょ、と考えるごくごく普通の感覚があなたの四暗刻産出量を減らしていることにそろそろお気づきになられても…。
C 南2局 東家 5巡目 原点からマイナス8000点
(※![]() が1枚切れ、他は生牌)
が1枚切れ、他は生牌)
私の選択=![]() 切り
切り
よく見る手牌ですね。
赤とドラを使えば喰いタンでも大満足の親マンコースですので、なんのためらいもなく![]() に手が伸びるはずです。
に手が伸びるはずです。
もちろんその思考を否定するつもりはありませんが、手牌はいま重要な分岐点を迎えようとしていることにも気づくべきです。
その分岐点とは、七対子への道か、四暗刻への道か、という打ち手であれば誰もが通る関門のこと。
手牌に戻ります。
(※![]() が1枚切れ、他は生牌)
が1枚切れ、他は生牌)
尖張牌の![]() が暗刻になったので、これは四暗刻へ一直線と考えるのは早計で、
が暗刻になったので、これは四暗刻へ一直線と考えるのは早計で、![]() と
と![]() というスジトイツが5巡目にして組まれていたことに七対子の香りがプンプンしてしまうのも事実なのです。
というスジトイツが5巡目にして組まれていたことに七対子の香りがプンプンしてしまうのも事実なのです。
つまり、ツモ![]() で四暗刻へのGOサインが出されたかどうかはまだ微妙なのです。
で四暗刻へのGOサインが出されたかどうかはまだ微妙なのです。
いま5巡目ですから、この分岐の限界巡目を定めておく必要があります。
そもそも、七対子と四暗刻は『天秤にかけてはならない』手役同士なので早めにどちらかへの決断を下さなければならないのです。
9巡目がハーフタイムですから、その2巡前、つまり中盤戦を迎える7巡目には天秤打ちを解消すべきです。
幸いにして四暗刻の種はすでに揃っていて![]()
![]()
![]()
![]() が暗刻になることを祈ればいいだけです。
が暗刻になることを祈ればいいだけです。
ここで注意すべき点がひとつ。
シュンツ手でよく5メンツ目の種を残しながら組み合わせを作っていく技法があるように、四暗刻も5つ目の種を残しながら打っていくとより精度がアップします。
![]()
![]()
![]()
![]() の他にある孤立牌は、
の他にある孤立牌は、![]() を切ると
を切ると![]() と
と![]() の2種が残ります。
の2種が残ります。
![]() が1枚切れ、
が1枚切れ、![]() が生牌ということを踏まえると、もうひとつ暗刻が増えて四暗刻のイーシャンテンになったときは、安全牌などを残さず、1枚切れの
が生牌ということを踏まえると、もうひとつ暗刻が増えて四暗刻のイーシャンテンになったときは、安全牌などを残さず、1枚切れの![]() も残さず、生牌の
も残さず、生牌の![]() をキープしておくのです。
をキープしておくのです。
こうしておけば、イーシャンテンの道中で![]() が重なったら、他の暗刻候補との比較ができて、場合によってはドラ
が重なったら、他の暗刻候補との比較ができて、場合によってはドラ![]() のトイツ落としをして四暗刻を狙うというミラクルショットすら想定できるのです。
のトイツ落としをして四暗刻を狙うというミラクルショットすら想定できるのです。
逆に7巡目を迎えても暗刻が増えなかった場合には暗刻の![]() を1枚外して七対子への道を行けばいいのです。
を1枚外して七対子への道を行けばいいのです。
幸いにして孤立牌の![]() と
と![]() は七対子の種としてふさわしいものですし、新たに1枚トイツ候補を入手できるわけですから、テンパイはかなり容易なものとなるでしょう。
は七対子の種としてふさわしいものですし、新たに1枚トイツ候補を入手できるわけですから、テンパイはかなり容易なものとなるでしょう。
七対子も四暗刻も狙って作る役。
シュンツ手や混合手、あるいは仕掛け役と天秤にかけながら作っていく役ではないことを肝に銘じておきましょう。
また、七対子と四暗刻も似て非なるものと考えて打っていって欲しいものです。