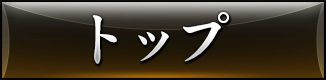





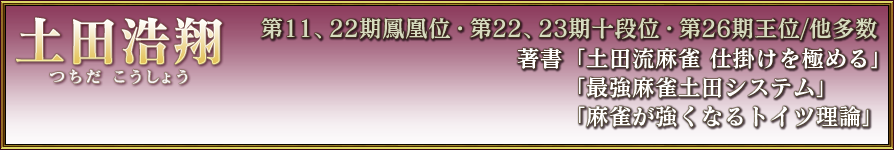
番外「飯田正人 永世最高位を偲んで」2012/5/23
飯田正人(いいだまさひと)永世最高位が永眠されました。
享年63歳、プロ界の至宝を失うにはあまりに早く、あまりに酷く、神様どうして?と何度でも問いかけたくなります。
飯田正人という名前を始めて目にしたのは、私が高校に入ったばかりの頃ですから、今から35年ほど前、昭和50年代前半に刊行されていた麻雀専門誌でした。
小島武夫・灘麻太郎・古川凱章・田村光昭・青柳賢治というビッグネームの下に、安藤満・荒正義・金子正輝と共に、一流若手プロとして名を連ねていたのです。
私は昭和63年に『日本プロ麻雀連盟』の門を叩いたため、飯田さんのいた『最高位戦』との交流は少なく(私がペーペーだったことがその最大の理由です)、<王位戦>や<マスターズ>という交流タイトル戦だけが、飯田さんの胸を借りられる舞台でした。
感化されやすいタイプの私は、連盟の花形選手たち(小島武夫・灘麻太郎・安藤満・荒正義)の牌譜を採ったり、対局したりしているうちに、連盟の打ち手たちのレベルの高さだけを誇りに思い、最高位戦?みたいな、いま思えば恥しくなる価値観でプロ生活を送っていました。
ところが、王位戦やマスターズの舞台で飯田さんの胸を借りるたびに、その凡庸でそこの浅い価値観は180度変わっていきました。
よくわからないうちに負けている、最初はそんな印象でしたが、何度も胸を借りていると、なんなのこの圧力は、なんなのこの強さは!と、屈伏させられていきました。
このイーシャンテンに![]() を引いてきて、
を引いてきて、![]() を切ってリーチをかけ、
を切ってリーチをかけ、![]() をピシッとツモアガリされたとき、私はいつもどうして?という疑問符を付けていました。
をピシッとツモアガリされたとき、私はいつもどうして?という疑問符を付けていました。
勝ち続けている人でしたから<強い>のはイヤというほど理解できたのですが、私が目の当たりにしてきた連盟の花形プロたちとは明らかに違う<泥臭さ>を感じていたのも事実です。
こういうイーシャンテン構えは、平成の時代の今でこそ当たり前のように受け入れられていますが、昭和の時代では「ヤボったい打ち手」の代名詞でした。
345や234の三色が見える手牌で、何故にダブり牌の![]() を抱えておく必要があるのか?その
を抱えておく必要があるのか?その![]() や
や![]() を暗刻にしてテンパイさせてもピンフ役が消えてしまうじゃないか、更には、
を暗刻にしてテンパイさせてもピンフ役が消えてしまうじゃないか、更には、![]() を引っ張って3メン受けのソーズから埋まってしまったら、ソバテンリーチになってしまうじゃないか。それに、
を引っ張って3メン受けのソーズから埋まってしまったら、ソバテンリーチになってしまうじゃないか。それに、![]() を先切りしておけば、
を先切りしておけば、![]()
![]() 待ちになったとき、
待ちになったとき、![]() が出てきやすくなるじゃないか。等々の理由で、飯田さんの打ち筋は「ヤボったい打ち手」の典型のように語られていたのです。
が出てきやすくなるじゃないか。等々の理由で、飯田さんの打ち筋は「ヤボったい打ち手」の典型のように語られていたのです。
でも、飯田さんは、最期の公式対局となった今年の『モンド名人戦』の最終局まで、自身の流儀を貫き通しました。
プロの間では、「飯田はヘタだ」とか「飯田は素人の頂点だ」とか、その強さは評価しつつも、その打ち筋を批判的に論ずる向きもありましたが、飯田さんは笑って受け流していました。
飯田さんと対局後に感想戦のような会話をすると、局面のとらえ方がとても繊細であることに驚かされます。と同時に、私の質問の真意を素早く見抜いた回答をしてくれます。
<大魔神>と畏れられる突進力や、アイアンハートだけがクローズアップされがちですが、実際は違います。
もちろん、<攻める>と決めたときの怒涛の突進力や揺れないハートは、一流プロの必要条件として持ち合わせていますが、超一流プロとしての十分条件も兼ね備えていたのです。
それは、類い稀な2つの<洞察力>です。
ひとつは、対局相手の挙動を見抜く<目>。
そしてもうひとつは、対局相手の心の動きを見抜く<眼>。
この2つの精度によって、超一流の領域を最後の最後まで堅持できたわけです。
私は飯田さんが人の悪口を言ったり、打ち筋の批判をしたりするシーンを見たことがありませんし、プロの間で、飯田さんの人となりについて悪く言う人に出会ったことがありません。
恐らく<人格者>という点において、飯田さんの右に出るプロは存在していないのでは・・・と思えるほど、飯田さんの人間性というか人間力は眩しいほど輝いていました。
そして、飯田さんの<歌>。
1度でも聴いたことがある人ならすぐにその人柄に納得がいくと思います。
<歌>を聞けばその人の<心音>が見えてくると言われていますが、まさにその通り。美声とかそういう問題ではなくて、飯田さんの歌には<愛>がいっぱい詰まっていました。
人に対する優しさ、人に対する思いやり、人に対する無償の愛が、飯田さんの歌には溢れていました。
飯田さんは『モンド名人戦』の全収録が終わった直後、さりげなく私にこう言ってくれました。
「ツッチー、ありがとうな」
私の耳に鮮烈に残っている飯田さんのこの言葉。
なんてあったかいんだろう。
声を思いだすたび、涙があふれでてきます。
『最高位』を10度獲り、『永世最高位』として永遠に人々の記憶に受け継がれていく不世出の打ち手、飯田正人。
どうか安らかにお眠りください。









