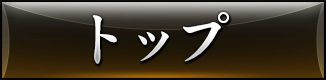





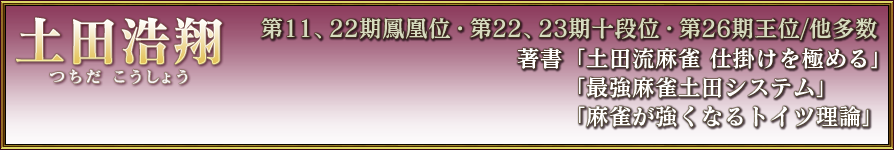
第五十四打「基本から離れよう」 2022/02/18
序盤に切り出す6枚、この6枚に打ち手の麻雀能力が凝縮されています。
能力の高い打ち手の序盤は変幻自在、けっして毎局似たような6枚にはなりません。
序盤の切り出しの<基本>は
(A) 孤立字牌→孤立1・9牌→孤立2・8牌
(B) 孤立1・9牌→孤立字牌→孤立2・8牌
(C) 孤立2・8牌→孤立1・9牌→孤立字牌
(D) 孤立2・8牌→孤立字牌→孤立1・9牌
こんなところでしょうか。
(C)と(D)は珍しく2・8牌からの切り出しになっていますが、オーソドックスなピンフ系には向かわない手筋、たとえば七対子や対々和、更には一色手など、1・9・字牌を使いたいときの<基本>です。
<基本>を会得したあとは、その<基本>に忠実に打ち続けることを是とする打ち手も多いようですが、その忠実さが自身の進化を止めていることもあります。
<基本>を知り<基本>を崩す勇気も時には必要で、マンネリ化した序盤は対局相手から見れば、分かりやすいし御しやすいという事実も知っておいたほうがいいでしょう。
東2局の親の配牌です。
第1打は?
もう数えきれないくらい繰り返していますから、![]() から、もしくは
から、もしくは![]() から切り出していくはずです。
から切り出していくはずです。
最初のツモが![]()
そして3巡目に![]() を引いてきました。
を引いてきました。
打![]()
これも異論はないかもしれません。
親番ですから、水も漏らさぬ構えで打つことは<基本>ですよね。
4巡目のツモは![]() で
で
さてここから何を切るのか?
![]() がドラですから
がドラですから![]() でしょうか、それとも
でしょうか、それとも![]() になるのでしょうか。
になるのでしょうか。
![]() を切ってしまうと
を切ってしまうと![]() が余り牌に見えるので、
が余り牌に見えるので、![]() のほうを選ぶ打ち手が多いのかもしれません。
のほうを選ぶ打ち手が多いのかもしれません。
![]()
![]()
![]()
![]() と切り出せば
と切り出せば
![]()
![]()
![]()
![]() と切り出せば
と切り出せば
初級〜中級クラスで身につけた<基本>に忠実に打てばこうなります。
もう1度配牌に戻ってみます。
ここからの第1打が![]()
次にツモ![]() で打
で打![]()
そして3巡目ツモ![]() で打
で打![]()
4巡目のツモ![]() で、ようやく場に2枚切れとなった
で、ようやく場に2枚切れとなった![]() を切りました。
を切りました。
この打ち手の河は
![]()
![]()
![]()
![]()
同じ配牌とツモであるにもかかわらず、まったく違う河と手牌になっています。
<基本>に忠実に打てば4巡目までの手牌は
もしくは
となるため、
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
もしくは
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
これら9種類34枚の牌がアガリに近づくメンツへの受け入れとなっています。
それに対して異質な河の方の手牌では
となっているため、
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9種類36枚の牌がアガリに近づくメンツへの受け入れとなっています。
不思議ですよね。
<基本>に忠実に打っていたはずなのに、メンツ作りへの受け入れ枚数が異質な河の手牌より少なくなっているのです。
損が無い選択を続けるための序盤だったはずなのに、組み合わせ作りの効率が若干下がっているという現実。
更にいえば、<基本>に忠実に打ってしまうと、安全牌候補の![]() が手牌に残らなくなるのです。
が手牌に残らなくなるのです。
これは早い相手からのリーチに対して無防備であるということに他なりません。
また、序盤の河が<基本>に忠実であるということは、イコール複合形を抱えて打つため、相手に読まれやすい手牌になっているということに他なりません。
この手牌ではマンズに傷が残ります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() もしくは
もしくは ![]()
![]()
![]()
![]()
4巡目でこの形になっています。
手牌全体を見渡して、雀頭候補が唯一この![]() であるために、
であるために、![]() か
か![]() が引けたり、ピンズやソーズのカンチャンが首尾よく埋まってくれれば、
が引けたり、ピンズやソーズのカンチャンが首尾よく埋まってくれれば、![]() が雀頭で生きます。
が雀頭で生きます。
5巡目以降、何を引いてくるのか分からないのだから、![]() を雀頭に想定しておくことは当然だろうと考えるのが普通です。
を雀頭に想定しておくことは当然だろうと考えるのが普通です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() もしくは
もしくは ![]()
![]()
![]()
![]()
この形に対して
![]()
![]()
![]()
![]()
こちらは雀頭候補を早々にリャンメンに決めています。
更には河が
![]()
![]()
![]()
![]()
という切り出しなので、ペン![]() 待ちになっても、
待ちになっても、![]()
![]() 待ちになっても和了率はぐんと上がるはずです。
待ちになっても和了率はぐんと上がるはずです。
<基本>に忠実に打つと、マンズの複合形の処理にひと手間かかる可能性があります。
すんなりカンチャンが埋まれば問題はないのですが、イーシャンテンまでカンチャンが埋まらないと、![]() や
や![]() を中盤に切り出さなければならない手順が生まれ、相手の攻撃に窮してしまう恐れがあります。
を中盤に切り出さなければならない手順が生まれ、相手の攻撃に窮してしまう恐れがあります。
麻雀能力の高い打ち手は配牌を見たときに
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
このマンズの形が傷にならぬよう、序盤の切り出しに工夫を加えていくのです。
もちろん、ごくたまに![]() や
や![]() があっさり引けて、傷口がアッという間に塞がることもありますが、そんな期待は持たずに打ったほうがアベレージは上がります。
があっさり引けて、傷口がアッという間に塞がることもありますが、そんな期待は持たずに打ったほうがアベレージは上がります。
親でこの配牌、テンパイ止まりではなく、何としてもアガりをと考えたとき、第1打に何を切るのか?けっこう難しいはずです。
<基本>に忠実に打てば、![]() や
や![]() からの切り出しになるでしょう。
からの切り出しになるでしょう。
ドラの![]() がポンできたりアンコになれば、マンズ・ピンズがチー・ポン自在となるからです。
がポンできたりアンコになれば、マンズ・ピンズがチー・ポン自在となるからです。
でも手牌は七対子のリャンシャンテン。
子方に警戒されないまま、7〜8巡目あたりに「ロン、9600」と言えるビッグチャンスが訪れていることも事実。
![]() や
や![]() という七対子では待ちごろの牌を序盤に切り出すのはもったいないなと感じる打ち手は、
という七対子では待ちごろの牌を序盤に切り出すのはもったいないなと感じる打ち手は、![]() や
や![]() を第1打に選ぶはずです。
を第1打に選ぶはずです。
親だから、水も漏らさぬ構えで打ちたいから<基本>に忠実に打つ。それも悪くない考え方ですが、アガり率を上げるためには<基本>を崩すことも必要になってきます。
アガりたいから組み合わせをミスしたくない
アガりたいから効率よく打たないと
アガりたいから字牌はさっさと処理しないと
打ち手はアガりたくなればなるほど<基本>にすがり始めます。
でも相手3人がいる実戦においては、その<基本>が通じない局面が多々存在することも知っておいたほうがいいでしょう。
序盤に切り出す6枚には、打ち手の意思が試されています。
麻雀への想いも託されているでしょう。
マンネリ化はできるかぎり避けましょう。
(A)パターンから(D)パターンまでの序盤があったとするならば(もっともっと多いかもしれませんが)、あらゆるパターンを駆使しながら、自分の目指すゴールに向かって1歩1歩踏み出していって欲しいなと思います。









