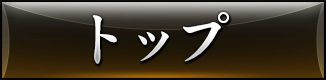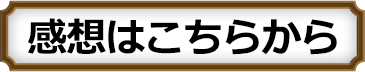- 第10話牌操作のモヤモヤを解決
- 第9話壊れないお椀
- 第8話2020年、娯楽の危機
- 第7話人和が役満になっている謎
- 第6話30倍の法則
第5話 麻雀って、何が楽しいんですか?
これだけマニアックに、仕事でもプライベートでも麻雀ばかりを追求していますと、自然と友人や仕事の繋がりの仲間は、麻雀好き一色になります。
時にはお酒を飲みながら他愛もない話もしつつ、その中でしばしば話題になるのは、「麻雀は何故こんなに面白いのか?」という話です。
もちろん正解などは無い問いなのですが、個人的な答えを聞かれた場合は、「多様性」と答えています。
それは麻雀というゲームが持つ「器の広さ」と言い換える事もできます。
麻雀があまりにも多様なゲーム性をもつために、色々な戦略や攻略法を打ち手は考えます。
まず大きな部分として、攻撃を重視するか守備を重視するかというのは打ち手によって大きく分かれますが、どちらが有利か一概に言えないのが面白いです。
私はせっかちで我慢が足りないタイプですので、すぐに攻撃型になってしまうのですが、私の感覚ではこれらは多数決の関係になっていて、4人で麻雀している時に、
3人が攻撃型、1人が守備型⇒攻撃型が有利
2人が攻撃型、2人が守備型⇒概ね良い勝負
1人が攻撃型、3人が守備型⇒守備型が有利
という感覚があります。
もちろん、これにも賛同を頂ける方と、そんな事はない、と反論される方もいらっしゃると思いますが、そういった多様な考え方を麻雀は受け止めてくれる、というのが面白いと感じています。
もちろん
4人が守備型⇒全員が洗面器の水に顔を浸けているような我慢の展開
4人が攻撃型⇒嵐のような乱打戦
というような事も考えられますね。
さらには、鳴きを重視した戦略にするか、門前を重視した戦略にするかというのは、真逆に近い打ち方ではありますが、どちらの戦略を打ち手がとっても、麻雀というゲームは、受け止めてくれます。
もっと言えば、これらの戦略をずっと変えずにいるという必要もなく、一日の中で、または一生の中で、絶えず違う打ち方を模索するという事も可能です。そしてその間、麻雀という器はそれらの多様な打ち方を受け止め続けます。
大きな部分での戦略もそのような案配ですから、細かい戦術レベルになると、さらに物凄い多様性があります。
即引っかけをやるかやらないか、染めるか染めないか、三色を無理にでも狙うか狙わないか、九種九牌で流すか、国士を狙うか、などなど、それぞれについて麻雀打ちであれば、それぞれの局面で考え方が分かれる部分だと思いますが、絶対的な正解というものが存在せず、各自の打ち手が、違う考え方を持って勝負に挑みます。
結果についても「リーチしてたら裏ドラ3つ乗ってトップだったよー(。>_<。) 」と、結果論をグチグチ言う私のような人もいれば、「結果論は結果論です。結果論を言ってたら麻雀うまくならないです。」のように、結果論に全く興味持たない人もいます。
また、確率などを中心に考えるデジタルという考え方が若い人を中心に最近主流になりつつありますが、私のようにIT会社を経営していながら、何故かオカルトに染まってしまっている人もいます。
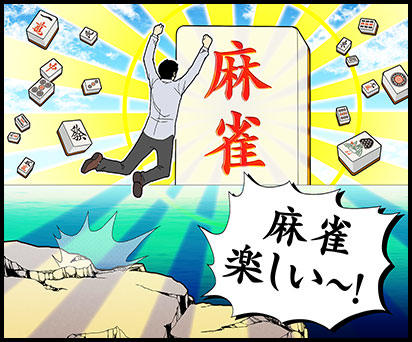
私は無宗教ですが、これは、もはや神様を信じるか信じないかぐらいの、信仰の違いと同じぐらい相容れない考え方のギャップと思います。しかし、そのような思想の国境を越えて、同じ卓を囲んで、楽しく勝負する事は可能です。
このように、全てを受け止める事の出来る大きな器をもった麻雀は、あまりにも多様性があり、皆が安心してその海に飛び込んでいくのです。